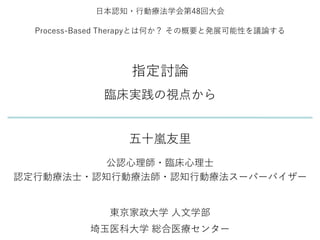
ProcessBasedTherapy_JABCT2022_Discussion1.pdf
- 1. 指定討論 臨床実践の視点から 五十嵐友里 公認心理師・臨床心理士 認定行動療法士・認知行動療法師・認知行動療法スーパーバイザー 東京家政大学 人文学部 埼玉医科大学 総合医療センター 日本認知・行動療法学会第48回大会 Process-Based Therapyとは何か? その概要と発展可能性を議論する
- 5. 環境と人間の相互作用を見る ・この相互作用によって生じる「刺激ー反応ー結果」の循環に注目 ・人間の中に起きること(私的出来事)は刺激にも結果にもなる 認知行動療法における個別の問題理解 ①刺激 ②反応 ③結果 環 境 人 間 ③結果 環 境 ①刺激
- 6. 思 考 反 応 身 体 気 分 行 動 認知行動療法における個別の問題理解 人を、思考・気分・行動・身体の4領域に分けて整理する この4領域は、刺激にも結果にもなりうる
- 7. 問題を維持する悪循環と望むものを増やす良循環を見る ・環境と人間の反応の悪循環が問題を維持・悪化させ、 環境と人間の反応の良循環が望む生活に近づくコツ 認知行動療法における個別の問題理解 認知行動療法入門(熊野・鈴木・下山,2017) 思 考 反 応 ⾝ 体 気 分 ⾏ 動 ①刺激 ②反応 ③結果 環 境 人 間 ③結果 ①刺激
- 8. 生活歴から、反応パターンや4領域の特徴的な反応を理解する これまでにどのような刺激に対してどのように反応して、どのような 結果を経験してきたかを知る(学習歴を教えていただく) 認知行動療法における個別の問題理解 協働的実証主義 ・共感的理解の上で一緒に現状や問題を外在化する 過去 現 在
- 10. PBTの発想を臨床に用いる上で気になること 協働的経験主義姿勢は不要? 協働的経験主義が生み出しているものは何か? Cl.がTh.に感じる共感性 協働的感覚 自らが自らを理解した、導き出した、気づけたという感覚 能動性の向上(解決してほしい→解決しよう) Cl.が自分の特徴を自ら発見していく手続きを手放すことの影響? CFに対するCl.の確信度?納得感? CFに対するCl.の確信度は、介入技法の実践にも影響する? セルフコントロール能力を育むことに影響しないか
- 11. データからCFが提供されることで利用されないもの? 過去のエピソード。「縦断的データ」の期間が短い? Th.の面接中の行動観察や感じた感情や違和感などは不利用? PBTの発想を臨床に用いる上で気になること 過去 現 在 PBTで収集する データ範囲?
- 12. 継続で来談するクライエントは、 「このセラピストなら一緒に一緒にやってもらえそうだ」 「お金を支払う価値がありそうだ」 「以前より良くなっている」 と感じられなければ、来談は中断する。(小林,2014) そのために、 これまでのCBTのどの部分をPBTに置き変えるのか または、置き換えずに付加的に用いていくのか これまでのCBTのどの部分は引き続き保持して進めるべきのか という整理や議論が求められるのではないだろうか。 PBTの発想を現場に普及させるにはどのような課題がありそうか
