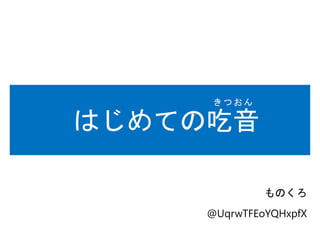
はじめての吃音_ネット公開版.pptx
- 8. 目に見えない障害 近年、発達障害を中心に目に見えない障害が認知さ れるようになってきた。 • 見た目は普通なので、〇〇はできて当然と期待さ れる。 • できないことが、本人の努力不足であるかのよう に言いくるめられる。 • それくらい誰にでもあることだと言われる。 理解されにくい。第三者からの「障害は個性」 7
- 9. なぜ吃音を学ぶのか? • 目に見えない障害であるために、誤解されやすい。 困難が軽視されやすい。 • 吃音は、本人の癖であり、本人も悩んでいないと 思われがち。 • 見た目は普通でも、本人は独りで悩んでいること が多い。→虐め、不登校、うつ病、自殺etc 8 吃音について知ることが、 吃音のある人の理解に繋がる
- 10. 吃音=どもり • 吃音とは、発話の流暢(りゅうちょう)性障害 • 原因不明。現在、決定的な治療法はない • 人口の1% ⇒ 国内で約120万人 • 男:女=3:1 9
- 12. 吃音の中核症状 11 ぼ、ぼ、ぼ、ぼくね 連発 (繰り返し) ぼーーーーーくね 伸発 (引き伸ばし) ・・・・・・ぼくね 難発 (ブロック) れんぱつ しんぱつ なんぱつ 中学生以上では、難発が一番多い
- 13. 吃音の不思議 • 人によって吃り方がばらばら • 苦手な音がある?特に、名前が言えない? • 緊張してるの? • タイミングをとると話しやすい? 12 よく分からない
- 16. 吃音による嫌な体験(自己紹介) 聴衆の反応 • 緊張し過ぎw • 名前忘れたの?w(難発の場合) • 落ち着いて! • 真似される • 外国人かよ!!爆笑w • 凍りついた空気=見ちゃいけないものを見た感じ 15
- 17. 吃音による嫌な体験(自己紹介) 吃音のある人の反応 • 恥ずかしい、死にたい、馬鹿にされた • 名前を忘れる訳ないじゃん(# ゚Д゚) 頭の中では、「私の名前は、大島 志乃です。」 と流暢に言える。⇐家で練習した • クラスの居場所ない。 • 心臓ばくばく。疲労感。汗。 • 自分はイケナイことをした。タブー、スティグマ 16
- 18. 負の連鎖 17 • 自己紹介の場面がトラウマになる • 名前を言えないのは、名前を忘れ たわけではないため、誤解による 嘲笑が恐怖になる。言いたいこと が言えない悔しさ • 当たり前のことが当たり前にでき ない劣等感⇐私はバカなの? • 自尊心の低下 • 憂鬱⇒精神的なストレス 次の自己紹介が怖い⇒予期不安
- 19. 予期不安 18 WWW
- 21. 予期不安の般化 • 春シーズン(新学期、面接etc)が怖くなる ⇒自己紹介の場面を避ける。スケジュールを事前 に確認 • 病院や美容室などの名前を言わなければならない あらゆる場所が怖い⇒自己紹介の場面以外にも派 生 • 名字や下の名前を変える人もいる。言いやすい音 20
- 23. 不安定な発話 22 吃音を隠したい 苦手な場面 (自己紹介、注文) 相手との物理的・ 心理的距離(初め て、慣れている) 周囲の環境(静かな 場所、がやがしした 場所) 会話の形式 (ターンテイキング、ダブルトーク) 苦手な音 (母音、破裂音) 苦手な言葉 (ありがとうございます、 お先に失礼します) 身体状況 (寝不足、緊張、 リラックス、 テンション) 会話の相手(先生、 家族、友達) 随伴行動 (体を揺らす、 手を振る)
- 24. 随伴行動・発話テクニック 随伴行動 • 足踏み • 腕を揺らす • 首を動かす • 目線を逸らす • 注意転換 23 発話テクニック • 言い換え(ホットコー ヒー⇒あたたかいコー ヒー) • 置き換え(語の順番を入 れ換える) • フィラー(ええと、 あの) • 解除(話すのをいったん 止める)
- 25. 吃音のある人が苦手な場面 • 音読、本読み(書いてる文章は頭の中では読めるが、 声を出そうとするとどもる。⇐書いてある文章を読 むだけなので、間が空くのは不自然) • メニュー注文(好きな食べ物がどもりそうなので あきらめる。又は、指差し注文、代わりに 誰かに注文してもらう) • 電話(相手の顔が見えないこと。身振り手振りが使 えないことが辛い。難発で声が出ないと、イタズラ 電話と勘違いされる) 24 個人差あり
- 26. 聞き手による多様性 • 早口な人と話すと難発で詰まりやすい ⇒ゆっくりな話し方の人とは吃音が出にくい • 家族や親友、恋人などリラックスできる人のほう がどもりやすい人もいる⇐ほどよく緊張している ほうが、どもらない。逆もあり • 先輩と話すときはどもりやすい⇐後輩と話すとき はどもりにくい。逆もあり • 赤ちゃんや幼児と話すときはどもりにくい ⇐これは結構な吃音のある人に当てはまる 25
- 28. 吃音をめぐる諸問題 • 「吃音=どもる」ことは、「噛む」ことと混同される ことが多い。しかし、吃音と噛むは、質的・量的に全 く異なる。 • 「吃音=噛む」と勘違いすることで、大した問題では ないと誤解されやすい。⇒吃音に悩むことは、くだら ない些細な問題と勘違いされる • 「噛む」ことは、一般的に「笑い」になりやすいので、 どもることも笑われやすい。しかし、どもりたくてど もっているわけではないため、バカにされたくない。 屈辱⇒話したくない 27
- 29. まとめ • 吃音はシチュエーション、環境、対人、言葉、 心理状態etcに依存する⇒365日24時間どもる人 は少ない≒0 • 吃音は十人十色 • 隠れ吃音の人は、様々な工夫をして対処してい る⇐見た目には分かりにくい 28
- 34. 吃音のある人との関わり方 • 「もっとゆっくり話しなさい」、「深呼吸して」、 「落ち着いて」は逆効果。効果なし • 吃音のある人が話し終えるまで、辛抱強く待つこ と。自然であること(驚いたり、不快そうな反応 は❌) • 話している途中で、言葉を挟まないこと。言葉の 先取りをしないこと(ただし、人による) • 焦らせないように話しかけること。 • 「私もどもることあるよ」は禁句。⇐反発心 33
- 36. レファレンス • 菊池良和(2012)『エビデンスに基づいた吃 音支援入門』学苑社 • 伊藤亜紗(2018)『どもる体(シリーズ ケアをひらく) 』医学書院 • 飯村大智(2019)『吃音と就職ー先輩から学 ぶ上手に働くコツ』学苑社 35
- 37. レファレンス • 吃音について|国立障害者リハビリテーションセンター http://www.rehab.go.jp/ri/departj/kankaku/466/2/ • 6 Tips for Speaking With Someone Who Stutters | Stuttering Foundation: A Nonprofit Organization Helping Those Who Stutter https://www.stutteringhelp.org/6-tips-speaking-someone- who-stutters • 飯村大智 2019年度「障害者週間」連続セミナー 社会が作る障害「吃音」:スティグマと就労から吃音を考 える 36
Notes de l'éditeur
- 私個人の主観による偏見や人生経験のバイアスもあるとは思いますが、近年「目に見えない障害」の方が注目されるようになりました。 身体に障害のある人を差別する訳ではありませんが、一見見た目には健常者と変わらないが、発達障害や精神障害などに悩む方にスポットが当たるようになりました。このような方が受ける誤解として、以下のようなことが挙げられます。 例えば、冗談が通じず真に受けてしまい、うまくコミュニケーションが取れないなどです。このような場合、その問題は障害を持つ当事者やその家族のせいにされてしまうことが多いです。また、周囲にの人間に相談しても、「考えすぎだ」や「自分もそれくらいはよくある」、「もっと大変な人はいる。あなたは大したことはない。」などと言われてしまったり、障害は個性だから言い訳にするななどど言われることもあるかもしれません。 このように「目に見えない障害」を持つ方が、誤解されてしまうことは多いです。
- では、なぜ今回吃音について学ぶのかと言うと、吃音のある人も先の話と同じような誤解と受けやすいからです。吃音は、「噛む」ことと同じであると誤解されやすく、また、言葉に少し詰まるくらいで別に気にするような問題ではないと思われてしまいます。また、小学校や中学校では、言葉を繰り返したりすることで虐められることも多いです。吃音のある人は普段は平気そうな顔をしていても、意外と吃音で悩んでいることが多く、助けを求めることは多いです。そのため、吃音について知ることが吃音のある人を救うことに繋がる可能性があります。次にスライドから、吃音について詳しく説明していきます。
- 吃音は、いわゆる「どもり」と呼ばれているものでありますが、最近の若い人の中では「どもり」という言葉すら聞いたことがない人もいるかもしれません。 吃音は、言葉がスムーズに話すことが難しい発話の流暢性障害と定義されています。発話障害という言葉を聞いたことがない人も多いので、当事者の中には「言語障害」という言葉を使う人もいるのですが、言語障害の場合、失語症などの言語機能を失っている、言語機能に障害のある人を表す場合が多いので今回は発話障害としました。 言語障害とは、脳内で正しい文章を組み立てられないことなどを表しているのですが、吃音は脳内では正常に言語を扱うことができているため、言語障害とすると誤解を招く恐れがあると思います。 また、残念ながら吃音は現在も原因不明であり、吃音に効果的な訓練法はあるにはありますが、あまり普及しておらず、また吃音に有効な薬などもありません、吃音は、全世界でどんな国にも1%存在していると言われています。日本国内では、およそ120万人の吃音当事者がいることになります。研究によって多少の違いはありますが、男女比は3:1くらいであり、男性の方が多いですが、女性もいます。
- まず、吃音とは「どもる」ことであり、以下の3つの症状があります。1つ目は、連発、繰り返しと呼ばれるもので、音の繰り返しを伴うものです。2つ目は、伸発、引き伸ばしと呼ばれるものです。3つ目は、難発、ブロックと呼ばれるもので、言葉が出せずに間が空いてしまうものです。吃音にはこの3つの症状がありますが、次に人が言葉を話す過程を簡単に見ていきます。
- まず、吃音とは「どもる」ことであり、以下の3つの症状があります。1つ目は、連発、繰り返しと呼ばれるもので、音の繰り返しを伴うものです。2つ目は、伸発、引き伸ばしと呼ばれるものです。3つ目は、難発、ブロックと呼ばれるもので、言葉が出せずに間が空いてしまうものです。吃音にはこの3つの症状がありますが、次に人が言葉を話す過程を簡単に見ていきます。
- 吃音は、かなり難しい障害です。その理由はいくつか考えられますが、具体的には以下のような現象があることが吃音の理解を難しくしています。 先のNHKの動画でもありましたが、どもると一言でいっても個人差が非常に大きいです。僕の場合は、あ行の音などでどもりやすいのですが、このようにある特定の音でどもることが多く、名前を苦手とする人は多いです。名前なんて、絶対に忘れるようなものではなく、生まれてから死ぬまで使い続けるものです。そんな名前が苦手とはどういうことなのでしょうか?どもっている人は、緊張しているから、慣れていないからどもるのでしょうか?名前に慣れていないことなんてあるのでしょうか? また、タイミングをとると話しやすいという話も出てきました。タイミングというと、僕たちは話の切り出し方が分からないことをタイミングが合わないと表現しますが、そういう意味なのでしょうか?このように吃音には未知な部分が多くあるように思われます。そこで、この講義では吃音のあることがどのような感覚を生じさせるのか説明していきたいと思います。
- では、吃音があると日常生活にどのような支障があるのでしょうか?勿論、全ての吃音が今回のようである訳ではありませんが、今回はケーススタディとして、多くの人が経験したことのある自己紹介の場面を扱います。 この写真は、ネットから拾ったきたものですが、ご存知の方はおられるでしょうか?詳しくは知りませんが、2ちゃんねるなどのネット掲示板やまとめサイトで一時期見かけることがあったので、見たことのある方もいるかもしれません。これは、押見修造さんの短編漫画「志乃ちゃんは自分の名前が言えない」で、主人公である女子高生大島氏乃のクラスでの自己紹介のコマです。
- 吹き出しにあるように、作品の中で「大島志乃」の「お」を発しようとしますが、「お」という音が難発で出せずに、「お」で足踏みするのですが、吃音はことばの順序を入れ替えると、スッと言えることがあります。 そのため、ネタとしてみんなを笑わすためではなく、声を出すために「しま おおしの」と名字と下の名前を入れ替えることで、なんとか切り抜けることができました。 ちなみに、以前吃音のない人から質問されたことがあるのですが、「頭の中でもどもっているのか?」という質問です。吃音は、少なくとも声を出さずに頭の中で話している限りでは自由自在にことばを操ることができています。 よくある誤解に、頭の回転が早くて口がついていかないなどと解釈される方がおられますが、少なくとも冷静である限り頭の中では明確に話したいことが準備されていると考えたほうが正しいです。
- 大島志乃の苦労とは、裏腹に、クラスからはこのような反応を受けてしまいます。緊張し過ぎ、名前忘れたの、落ち着いて、真似される、外国人かよと笑われる、なにか見てはいけないものを見たような顔をされるなどです。
- 一方で、どもった本人はどのようなことを感じているのでしょうか? 大勢の前で醜態を晒したのですから、恥ずかしい、文字通りの意味ではなく、死にたいくらい、恥ずかしい、辛いという情動反応が考えられます。吃音のない人でも、自己紹介で「噛んだ」際に恥ずかしい思いをするのですから、吃音のそれがそれ以上であることは想像に容易いです。 当事者として、ぐさっと突き刺さる言葉に「名前忘れたのw」という冗談交じりの反応です。「名前忘れたの?」というのは、言われた側からすると、そんな誰にでも当たり前にできることがあなたはできないのですか?と言われているように感じ、人格を否定されたような激しい屈辱を感じます。 この屈辱を増幅させることは、少なくとも頭の中では流暢に名前を言えるということ、更に苦手意識のあるものですので、失敗しないように練習してくることも多いです。例えば1人で声に出してリハーサルしている場面ではスラスラ言えているのです。なので、仮に練習していたとすると、余計にあの時できていたことができないという絶望感を味わうことになります。 また、どもっている時に、声帯が痙攣しているように、全身が緊張感で硬直しているため激しい疲労感を感じます。また、自分の番が過ぎてからも、自分は人前をいけないことをしたという周知心に苛まれます。人は、普段見慣れないものを見た時どのように反応したらよいか分からず、呆然としてしまいます。当事者としては、このときの腫れ物を見るかのような表情が脳裏にこびつき、軽いトラウマになります。 少し話はそれるのですが、日本ではよく「挨拶ぐらいできて当然」という考えが広まっている用に感じます。おそらく、学校の先生や大人の人から言われたことがある人もいると思いますし、自分自身もそのように考えている人も多いと思います。 しかし、吃音のある人からすると、この簡単な挨拶が連発や難発のためにスムーズにできず、挨拶を難しいと感じている人が多いです。勿論、言われなくても人にあったら「おはようございます」や「お疲れ様でした」などを言ったほうがいいのは理解しているのですが、「おはようございます」の「お」でつまってしまったり、「お疲れさまでした」の「お」で詰まって苦しい思いをするために、したくてもできないことが多いです。そのため、吃音あるあるとして「お疲れ様でした」を言わななくても済むように、本当は帰りたいのに、みんなが帰るまで待ち、その後で帰るという話もよく聞きます。 バカバカしく聞こえるかもしれませんが、当事者としてはこの挨拶がスムーズに、滑らかに行えずに、周りから「えっ。どうしたの?」と不思議がられることが怖くて仕方がないのです。
- このような体験を通して、例えば自己紹介が苦手な場面となります。また、本当に頭が真っ白になり、名前を忘れてしまったらまだしも、吃音の当事者は絶対に名前を忘れていないのであり、それを誤解されて笑われることは精神的に辛いものです。 また、このような言いたいことが思うように言えないことは悔しいものです。また、みんなが普通にできる、当たり前のことが当たり前にできないことは劣等感を生みます。 自分を頭が悪い人間であると疑ってしまうのです。特に、日本では、スラスラ話せること、饒舌であることが知性の高さ、有能であるかのように誤解している風潮があるため、余計にこのような思いは強くなります。 このような体験が、自尊心を低下させ、抑うつ気分を生じさせます。そして、ここが厄介なのですが、僕たちの脳はこの負の学習により、予期不安を生じるようになります。
- 予期不安とは、不安障害などの障害で用いられる用語ですが、多くの吃音はこの予期不安と切っても切り離せない関係にあります。 僕たちの脳は、縄文時代などのように「狩り」をして暮らしていた頃の生存本能として、一度起きた失敗が次に起こった場合、それは死を意味するので、二度と同じ失敗をしないように発達していきます。このため、僕たちの脳はこの経験を明晰に記憶し、恐怖心を感じさせるようになります。これが、予期不安と呼ばれるものです。
- この予期不安により、負のサイクルに苦しむことになります。どもることで、落ち込み、笑われたり、冷たい反応を受けることで「どもること=悪いこと」という認識を強化していきます。結果、吃りたくないという思いが予期不安に繋がり、なるべくどもらないように、話すの回避したりしていくよくになります。
- 予期不安は、自己紹介に限定されることではありません。自己紹介は、学期の始まりや、面接などで絶対に求められるものであり、多くの吃音のある人は春シーズンや夏休み明けの時期に不安を感じています。ある人は、就活の面接が怖いあまりに、面接の数時間前にお酒を飲み、不安を感じないようにして面接に行ったことがるという話を聞いたことがあります。この人は、特別お酒が好きだったり、アルコール中毒者であるという訳でもなく、面接に合格したいがあまりにこの選択をしたのです。吃音のある人の中には、アルコールを摂取することで、吃りにくくなり、流暢に話せるようになる人がいます。逆に、飲むことで吃りやすくなる人もいて、僕は後者のタイプに当てはまるため飲み会が嫌いです。 また、病院や美容室など名前を聞かれる場面を苦手とするために、できるだけ病院に行かないように我慢したり、できるだけ髪を切らないことなどもあります。 また、名前というと、毎回、毎回、名前で詰まることを避けるために本名の読み方を変えたり、ハンドルネームやビジネスネームを使用する人もいます。例えば、さとしをそうと読ませるなどです。 また、女性の吃音のある人では、恋愛において付き合う際に名前が呼びやすいかどうかを気にすることが多く、結婚して姓を変える際に、苦手な音で始まらないかなどを気にする人も多いです。吃音のない人からすると、これらの話は馬鹿げているというかあまり現実的には感じられないかもしれませんが、当事者としてはこれも深刻な悩みの一つだったりします。
- 次は、吃音のユニークな点について少しお話したいと思います。 なぜ、吃音が問題になるのか考えてみると、おそらく以下のような問題が重要なのだと思います。日本に住んでいる限りにおいて、英語が流暢に離せなくても困ることはほとんどありませんし、フィギュアスケートで有名なトリプルアクセルができなくても困ることはないと思います。 しかし、見る、聞く、話す、書く、読むなどの基礎的な能力において障害を持つことは、生きる上でリスクになります。先に挙げた、見る、聞く、書く、話す、読むなどはできて当然であると認識されていますし、例えば吃音のように見た目は普通であるせいもあり、期待されたようにできなかった時の落差が大きいのです。例えば、もし聞き手が短気な人だった場合、「なぜこの人は早く話さないのだと」イライラされてしまったりする訳です。 また、言いたい言葉が思い通りに出てこない、出せないという感覚は吃音独特の感覚だと思います。この自分の体をコントロールできない感覚は、吃音のある人に対して、少なからず「どうしようもない無力感」を与えます。 また、あとで説明しますが、吃音には解除、注意転換、置き換えなどの発話テクニックというものがあり、この発話テクニックを使わないと、テンポよく伝えられないことが自分自身を騙したり、裏切ったりする感覚を与え、時に罪悪感すら感じることもあります。
- 簡単に言ってしまえば、吃音のある人の発話は健常者(流暢話者)と比較して、発話が不安定であると言えます。 ある場面では、どもらないのに、ある場面ではどもるため、毎日が綱渡りをしているような感覚であります。例えば、周囲の音環境によって、流暢な発話が促進されたり、逆に阻害されたりします。僕の場合、居酒屋などのがやがやした環境では、静かな場所と比較して難発の出る頻度が明らかに増してしまうのですが、逆にガヤガヤした場所のほうが、自分の声を周りに溶け込ませることができるので話しやすいという吃音のある人もいます。 これは、皆さんの言う、話しやすい雰囲気とは異なるものだと思います。慣れない場所では、緊張して話が盛り上がらないなどのことはあるかもしてませんが、言葉に詰まりやすくなることはないと思います。他にも、苦手な音や、体のコンディションなどもありますが、こういった様々な要因から発話が影響を受けてしまうため、必然的に吃音のある人の行動範囲はこれらに制限されたものになってしまいます。
- 次に、吃音のある人がよく用いる随伴行動と発話テクニックについて紹介します。 随伴行動というのは、無意識であったり、意識的であったりはするのですが、ある人は話す際に腕を振りながら話すと吃りにくくなるため、いつも腕を振りながら話すなどがあります。このような人の場合、不思議かもしれませんが、電話など話している姿が見えないような状況を探すために、意図的にひと目に付かない場所に移動して電話をしたります。 注意転換というのは、具体的な方法というより抽象的なものなのですが、それが結果的に注意を対象から逸したり、切り替える行為を含むものを総称して呼んでいるものです。例えば、授業中に質問を当てられる際に、座席の順番通りに当てられる場合、自分の番がいつ回ってくるかが予想できるため、質問を当てられた際には、緊張で声帯が硬直し、声が出なくなるときがあるのですが、逆に不意に当てられた場合には、スラスラと答えられることがあります。これは、話す言葉の対象に注意を向けていなかったことが功を奏した例と言えます。 発話テクニックとは、この方法を使うことである程度どもらずに話せる方法のことです、有名なものに、言い換えや置き換え、フィラー、解除などがあります。 言い換えとは、ある言葉を同じ意味の言葉(つまり、同義語、シノニム)で置き換えることで吃音を回避する方法です。例えば、ホットコーヒーのホが言いづらく、「ホ、ホ、ホ、ホ」となるところを、「あたたかいコーヒー」と言い換えることで流暢に言えます。 また、置き換えとは、先の「志乃ちゃんは自分の名前が言えない」で出てきましたが、「おおしま しの」を「しま おおしの」と名字と名前を逆にすることで言いやすくなったりします。 フィラーとは、「ええと、や、その〜」などの言葉を示し、吃音のない人もよく使うと思うのですが、一般的には話すことがまだ決まっていない際に時間を稼ぐ便利な方法として用いられますが、吃音の場合はそうではありません。 僕は、難発で言葉が出にくく、タイミングが取りづらいと感じた際には、「ええと」を多用します。注意しないといけないのは、これらの手法はあくまで健常者に気づかれないように自然である必要があります。なので、「ええと、ええと、ええと、ええと、ええと〜」となってしまっては、明らかに不自然になってしまい相手に違和感を与えてしまう危険性があります。 発話テクニックは、一部の当事者からは吃音のある人達の文化の一種と表現する人もいるくらいであり、吃音のある人にとって身に染み付いてしまった癖のようなものかもしれません。
- 次に、最初に紹介した「自己紹介」以外の吃音のある人が苦手とする場面について紹介します。吃音のある人には、音読が苦手な人が多いです。音読は、小学校から高校くらいまで続きますが、吃音のある人は書いてある文字を読み上げる際に連発や難発になりやすいです。 これは、吃音のない人からすれば、書いてある文字を読み上げるだけの単純な作業くらいにしか感じないかもしれませんが、吃音のある人にとっては、言葉に詰まってしまうと、周りの人から不思議がられることが精神的なプレッシャーになり、 また、読めないと、漢字の読み方が分からない、英単語の発音が分からない、予習をサボっているなどと勘違いされやすいため、余計に周囲から誤解さらやすく苦手とする人が多いです。 吃音は、言葉の出だしで発生する確率が最も高いため、最初の一語を出すのにエネルギーを消費ます。しかし、斉読のようにみんなで声を合わせて読む時には流暢に読めるため、斉読を取り入れるのも一つの手段です。 また、メニュー注文も吃音のある人にとっては鬼門になりやすいです。これも、音読と同じであり、書いてある文字は頭の中では読めるのですが、いざ声に出そうとすると、言葉の出だしで躓くことが多く、また店員さんの???な反応により、店員さんから変な人だと思われているのではないかと精神的なストレスを感じてしまいやすいので、本当は食べたいメニューではなく、物理的に発声しやすいメニューを注文することが多いです。 そのため、吃音のある人にとって、口頭で注文するお店はハードルが高く、牛丼チェーン店の松屋などのように食券制のお店を選ぶことは吃音あるあるになっています。ですから、僕は出店などの屋台注文が苦手なのですが、メニューを注文する際に吃音のある人の代わりに注文してもらえることは、吃音のある人にとっては非常にありがたいです。 周りに助けてくれる人がいない場合は、指差し注文で「これください」ということも多いです。この場合、手元にメニュー表がある場合であれば指差し注文ができるので良いのですが、昔ながらの町中華などのように壁にメニューがぶら下げてあるお店は指差しがしづらく、そういうお店は意図的に回避するようになります。 また、電話も苦手とする人が多いです。これに関しては、相手の顔が見えない状態での会話自体に精神的なストレスを感じるというのは健常者の方でもよくあることだと最近知ったのですが、吃音のある人にとっての困難はそういう意味ではありません。 吃音のある人の中には、ボディランゲージや身振り、手振りなどのジェスチャーを活用することで吃音のによる喋りにくさを軽くしようとする人達がいます。しかし、電話の場合それが使えないことは、吃音のある人達にとって、とっても困ったことになります。 また、「もしもし」の「も」が、難発で詰まってしまうことも多く、相手からイタズラ電話と勘違いされやすく、それがトラウマになり電話を恐れる人も多いです。 あらゆる行為には、必ず慣れが生まれることで楽にスムーズに行えるように自動化されていくのが普通だとは思うのですが、吃音の人の場合、慣れても、まったく上達せず、逆に負の方向に強化されていく人もいます。 これらの理由により、吃音のある人は、僕も含めて、今で言えば、LINEなどのチャットツールを好む人が多いです。健常者からすると、いちいちテキストを打つのが面倒という人も多く、社会人であればとりあえず内線をかけることも多いと思うのですが、吃音のある人からすると、申し訳なくもありつつも、やっぱりチャットや電子メールにしてほしいと思ってしまうのです。 ただ、吃音は、現在はまだ不明なのですが、連発、伸発、難発といった症状の違いではなく、サブグループがあり、吃音Aタイプ、吃音Bタイプ、吃音Cタイプなどが存在し、そもそも全ての吃音のを一括にして扱ってよいのかという議論があります。そのため、必ずしも全ての吃音のある人に当てはまる訳ではないということは注意してもらいたいです。
- 次に、聞き手による多様性についてお話します。吃音のある人は、比較的ゆっくり話す方と多少早口になるクラタリング傾向のある人がいます。詳しくは説明しませんが、吃音とよく似たものにクラタリング(早口症)と呼ばれるものがあります。前者のゆっくり話す人達にとって、早口な人達は非常に会話のリズムが取りづらく症状が出やすくなり、苦手としやすいです。 勘違いされてしまうのですが、僕たちは別に早口な人が嫌いな訳ではないのですが、僕たちの身体は早口を拒否してしまうのです。結果的に、早口の人と話すことが難しくなるので、意図的に会話すらしないようになったります。 逆に、ゆっくり話す人と吃音症状も比較的出づらいために、会話の頻度も増えたりします。また、これもよく聞く話なのですが、家族や親友、恋人などリラックスできる人のほうが吃音が出やすい人もいます。 これは、スポーツで例えると分かりやすいと思うのですが、スポーツにおいて最適なパフォーマンスを行うには、体のコンディションを整える必要があります。試合で全力を発揮するためには、リラックスし過ぎでもなく、過緊張でもなく、程よい緊張状態であることが必要です。吃音のある人は、この程よく緊張した状態であることが、一番流暢に話しやすくなるために、あまり仲が良くない関係のほうが吃りにくいという皮肉が起きたりします。 勿論、逆の人もいますが、勘違いしてほしくないのは、どもることは聞き手に対して嫌悪感や苦手意識があるという訳ではないということです。ただ、身体が相手を拒絶しているのです。同様に、話す人の立場によって吃音の出やすさが変化します。 僕の場合ですが、先輩や後輩と話す時は心理的な安心感のためか、吃音も出にくいのですが、逆に同期の人だと同じ立場にいるせいか、吃音が出やすくなってしまいます。一般的には、上の立場にいるほうが、立場上の優位性が精神的な安心感を生み、比較的吃りづらくなることが多いように感じます。 また、これは比較的多くの人に当てはまるように感じるのですが、年齢的に幼い人と話す時は、吃りづらく流暢に話しやすいということがあります。人間は、赤ん坊などに話しかける際、幼児語、マザリーズと呼ばれる話し方を用いますが、マザリーズとは、普段よりやや高めのピッチ、ゆっくりとなる速度、大きくつく抑揚をつけた話し方のことですが、赤ちゃんや幼児と話す時には何故か流暢に話しやすいです。
- ここまで長々と吃音の特徴について説明してきました。吃音のある人には、流暢にどもらずに話せるときと、そうでない時のギャップが大きいことが分かります。 周囲の人からすれば、一日中その人と一緒にいることはないので、周りからは分かりづらいのですが、当事者としてはこの吃音が出る状態の存在があらゆる社会的活動にブレーキをかけることがあります。 本来は明るい人間でも、この吃音が出る時と出ない時のギャップのために、つまり、いつも活発に話している自分が、吃音が出る自分で塗りつぶされないように、あえてクールな人間や、大人しい人間を演じるようになります。人には、単一のパーソナリティだけではなく、多面的な側面が合って良いし、あるものだとは思うのですが、本来の性格を偽って生活することは苦痛で仕方がないものです。
- ここで、吃音と噛むことの違いについて説明します。 テレビ番組などでは、噛むことを笑いとして扱うことが一般的でありますが、吃音と噛むことを、質的、量的に別次元のものであります。多くの人は「吃音=噛む」と思っているので大した問題ではないと誤解しています。噛むことは、噛むことで当事者としては悩みの種かもしてませんが、吃音に悩むことは、つまらない些細な問題であると錯覚してしまいがちであります。 吃音のある人は、心の許せる人には自身のことを知ってほしいと考えている方が一定数おり、その人達からカミングアウトを受ける場面に遭遇するかもしれません。 その際には、相手の主張を否定せずに、受け入れるように意識してもらうだけで吃音のある人は安心感を感じやすいです。また、隠れ吃音の人はあまり当てはまりませんが、比較的吃音が目立つ方もいます。 噛むことは、一般的に笑いに繋がりやすいので、吃音も同じように笑われることが多いです。しかし、吃音は噛むと比べて、コントロールが効かないもの、どうしようもないものであり、わざとやっている訳ではありませんから、せっかく頑張って話しているのに、「何、その話し方。オカシイ、笑い」となってしまうと、言われて本人は心底傷ついてしまいます。 勿論、笑っているほうは、大した問題ではないと捉えているので笑っているのですが、例えば足に障害があり、自然に歩けない人を笑わないように、同じように笑ってはいけないということを知ってほしいです。
- まとめです。吃音は、周囲の環境や、対人関係、言葉、心理状態などに影響を受けます。そのため、365日24時間どもっている吃音のある人はめづらしく、場面によって様々な様相を含めて吃音なのです。 なので、ある1場面で吃っていないからと言って、「気にならないよ」や「吃ってないよ」などの言葉をかけるのは当事者にとってかなりショッキングなものであります。また、軽度の吃音を隠れ吃音と呼んだりするのですが、実は随伴行動や発話テクニックなどを駆使してサバイバルしているということを知ってほしいと思います。
- ここからは、吃音を社会学の視点から捉えてみようと思います。 スティグマとは、社会的な負の烙印であり、負の烙印とは、これを持つことで望ましくない存在として他人から蔑視や不信を受け、社会から十分に受け入れられる資格を奪うものとされてます。吃音の場合、詰まらずに話せることが当たり前であると思われているために、吃音などの非流暢な話し方は好ましくないものとされてしまいます。
- スティグマには、自己スティグマと社会的スティグマの2種類があり、自己スティグマとはスティグマを持つ自己への否定的態度であり、社会的スティグマとは、スティグマを持つ者に対する一般的偏見のことです。 吃音における自己スティグマとは、どもる自分は話してはいけないのだと自らに言い聞かせたり、劣等感、自己嫌悪に陥ってしまうことです。 また、吃音における社会的スティグマは、どもる人は緊張しやすいから、頼りなさそう。話すの苦手そうだから、あまり話かけないほうが良いのかなと判断してしまうこと。また、言葉が出るのを待ちたくない、変な話し方の人とは関わらないほうが良いなどの態度も社会的スティグマであると言えます。 特に、幼少期には吃音をウイルスのように扱い、吃音の真似をすると吃音がうつるなどのデマがあったりしますが、吃音の原因の大部分は遺伝的要因であり、一節によれば、環境要因3割、遺伝的要因7割と言われており、吃音になる遺伝子を持たない限りは、吃音の真似をすることで、吃音がうつることは考えにくいです。 ラヴソングの話
- そして、自己スティグマと社会的スティグマはお互いに影響を及ぼし合うものです。吃音のある人は、自分の話し方を否定することで、話すことを避けていくようになり、同時に吃音のない人はそのようにコミュニケーションを避けている人と積極的に関わりを持とうとしない限りは、吃音のある人とない人との交流は生まれなくなってしまいます。
- では、吃音のある人は、話すのが苦手だとしても、話すこと自体が嫌いなのでしょうか? 僕としては、極論として話すのが嫌いな人はいないのではないかと思っています。勿論、話の合う人、合わない人がいて、全ての人に話したい訳ではありませんが、趣味の合う人同士であれば会話は弾むものですし、やはり誰でも自分の考えを誰かに伝えたいものだと思います。 言うまでもなく、吃音のある人も話したいのです。それどころか、普段話すのを我慢しているために、話せる人には余計に話したくなってしまうこともあります。
- では、吃音のある人とはどのように接するのが良いのでしょうか?人との関わり方に正解も不正解もありませんが、比較的以下のことが推奨されています。 吃音のある人でも、クラタリングタイプの人は、意図せずに早口になってしまう傾向があります。その人としては、早く話したくて早く話している訳ではないので、「もっとゆっくり話しなさい」は禁句とされています。 また、「深呼吸して」、「落ち着いて」も逆効果であったりします。吃音は、焦るから、緊張するから出るという簡単なものではないので、本人としては精神状態は落ち着いているつもりであったり、また落ち着こうと努力している場合が多く、その人に向かってそのような言葉をかけることは本人の努力を否定することになるため、あまりおすすめできません。 次が、関わり方として最も推奨されているものなのですが、吃音のある人が話している時は、話し終えるまで辛抱強く待つことが適切であるとされています。また、その際に怪訝な表情をしたり、イライラした態度を出さないように努めてもらいたいです。 なぜなら吃音症状が出ている際に、イライラしたり、不機嫌そうな反応をされると、吃音のある人は心理的なプレッシャーから余計にどもってしまうためです。また、これに付随することですが、基本的には、じれったいからと言って吃音のある人が話している際に、言葉を挟んだり、言葉の先取りをしないことが推奨されています。これは、途中で言葉を挟んだり、先取りをされてしまうと、本人が自分の意志を受け取ってもらえなかったというフラストレーションを感じてしまうからです。 また、言葉の先取りに関しては、気をきかせて先取りしたものの、実は本人が意図していたことと違うことを誤って受け取ってしまう可能性もあるため、あまりおすすめはできません。しかし、話し相手との情緒的やり取りが行えていたり、お互いに仲の良い関係である場合には、言葉の先取りがコミュニケーションの手助けになる場合もありますので、やはり相手の意志を尊重することが大事であります。 また、近年吃音当事者の中でカミングアウトが広がってきており、心の許せる人に頑張って打ち明ける人も増えてきています。この時、当事者の人は孤独に悩んでいることを理解してほしくて、カミングアウトしているため、安易に「全然気にならないよ。私もどもることあるよ」と言ってしまうと、この人は私のことを全然理解していない。カミングアウトしなきゃ良かったとガッカリされてしまいますので、「そうなんだ。教えてくれてありがとう」などの言葉をかけるのが適切であると思います。
- 先のスライドでは、少し細かく説明しましたが、簡単に言えば、聞き手の「どもってもいいんだよ」という姿勢が重要です。 吃音のある人は、ほとんどの場合、自身の吃音を嫌っていますので、聞き手である皆さんに吃音は悪いものではないという姿勢があるだけで、吃音のある人は精神的に話しやすくなります。本日は長い時間お付き合いいただきありがとうございました。発表内容は以上になりますが、もう少しだけお話させていただきたいと思います。
- 参考文献は以下のようになります。
- 参考URLはこちらになります。