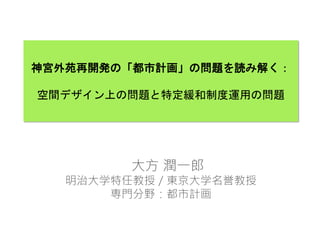
神宮外苑再開発の何が問題か〜「都市計画」の視点から読み解く
- 2. 神宮外苑再開発の「都市計画」の2つの問題: ① 空間デザイン上の問題: 公園を含む外苑地区の施設再整備計画が、公園や市街地のデザイ ンとして妥当なのか、という問題 ② 特定緩和型都市計画制度の運用の仕方の問題: 上記のデザインを実現するため、 公園まちづくり制度 と地区計画 の2つの仕組を使って建築規制を緩和しているが、 これらの「特定緩和型都市計画制度」の使い方(=規制緩和の仕 方や程度)が制度の本来の目的に即しているのかという問題と、 計画の決め方(=決定に至る審議の過程)がフェアで適正なもの であったのか(透明性・客観性・市民意見の反映・公平公正性) という問題。
- 3. どんな場所か
- 4. 土地・建物所有状況 https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/bosai/toshi_saisei/data/jinguu_kentou01_07.pdf
- 9. どんなプロジェクトか
- 10. 神宮外苑地区「公園まちづくり計画」による再整備計画の概要 (2021年7月に採択された「公園まちづくり計画」)神宮外苑地区公園まちづくり計画:公園まちづくり計画の概要 <https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/bosai/toshi_saisei/data/kouen_teian_gaiyo_01.pdf> ※本資料の記載の内容は、 現時点での計画であり 、 今後の行政協議及び詳細検討により 変更になる可能性があり ます。 1 計画概要 計画地 東京都港区北青山一丁目、 北青山二丁目、 新宿区霞ヶ 丘町の各一部 地域地区 第一種中高層住居専用地域・ 第二種中高層住居専用地域・ 第二種住居地域・ 商業地域・ 第二種風致地区・ 都市計画公園・ 第一種文教地区・ 防火地域・ 準防火地域・ 高度地区 指定容積率 200・ 600% ・ 700% 基準建ぺい率 ( 用途地域) 60% ・ 80% ( 商業地域のみ) 計画区域面積 約28.4ha 延床面積 約580,300㎡ ※TEPIA( 既存建物) は除く 最高高さ 約190m 解体着工 2022年 竣工 2036年( 2027年~ 段階的に運用開始) 主要な 施設名称 ラ グビー場棟 複合棟A 複合棟B 公益施設 TEPIA (既存建物) 文化交流施設棟 野球場 球場併設ホテル棟 事務所棟 絵画館前 テニス場棟 敷地面積 約43,480㎡ 約12,100㎡ 約14,710㎡ 約6,080㎡ 約8,760㎡ 約69,040㎡ 約13,170㎡ 約40,550㎡ 計画容積率 150% 900% 200% - 150% 150% 1150% 200% 延床面積 約76,700㎡ 約127,300㎡ 約30,300㎡ - 約2,000㎡ 約115,700㎡ 約213,000㎡ 約15,300㎡ 頂部建物高さ 約55m 約185m 約80m - 約6m 約60m 約190m 約15m 用途 ラ グビー場 文化交流施設 店舗 駐車場等 オフ ィ ス 商業 駐車場等 スポーツ関連施設 宿泊施設 駐車場等 - 公園支援施設 商業等 野球場 宿泊施設 商業 駐車場等 オフ ィ ス 商業 駐車場等 テニス場 駐車場等 東京体育館 三井ガーデンホテル 国立競技場 聖徳記念絵画館 絵画館前 広場 文化交流施設棟 ( つなぎスポッ ト ) ラ グビー場棟 複合棟B TEPIA ( 既存建物) 複合棟A 野球場/ 球場併設ホテル棟 保全緑地 事務所棟 青山 OMスク エア 中央 広場 新宿区 港区 渋谷区 外苑東通り いち ょ う 並木 絵画館前 テニス場棟 スケート 場 御観兵榎 外苑キャ ン パス にこ にこ パーク 地区計画の区域 促進区の整備計画を進める区域 公園まちづく り 計画の区域 街区境界 敷地境界 区界 ■計画概要 ■配置図 ■位置図 ■イ メ ージパース( 東側から 計画地を望む) 国立競技場 秩父宮 ラ グビー場 伊藤忠商事 東京本社ビル 青山 OM スク エア 聖徳記念絵画館 東京体育館 神宮球場 第二球場 明治神宮外苑 テニスク ラ ブ 軟式野球場 テピア JSCテニス場 JAPAN SPORT OLYM PIC SQUARE 日本青年館・ 日本スポーツ 振興ビ ル THE COURT 神宮外苑 JR千駄ヶ 谷駅 JR信濃町駅 東京メ ト ロ・ 都営大江戸線 青山一丁目駅 東京メ ト ロ 外苑前駅 都営大江戸線 国立競技場駅 公益施設
- 11. 神宮外苑地区「公園まちづくり計画」による再整備計画の概要 (2021年7月に採択された「公園まちづくり計画」)神宮外苑地区公園まちづくり計画:公園まちづくり計画の概要 <https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/bosai/toshi_saisei/data/kouen_teian_gaiyo_01.pdf> ※本資料の記載の内容は、 現時点での計画であり 、 今後の行政協議及び詳細検討により 変更になる可能性があり ます。 1 計画概要 計画地 東京都港区北青山一丁目、 北青山二丁目、 新宿区霞ヶ 丘町の各一部 地域地区 第一種中高層住居専用地域・ 第二種中高層住居専用地域・ 第二種住居地域・ 商業地域・ 第二種風致地区・ 都市計画公園・ 第一種文教地区・ 防火地域・ 準防火地域・ 高度地区 指定容積率 200・ 600% ・ 700% 基準建ぺい率 ( 用途地域) 60% ・ 80% ( 商業地域のみ) 計画区域面積 約28.4ha 延床面積 約580,300㎡ ※TEPIA( 既存建物) は除く 最高高さ 約190m 解体着工 2022年 竣工 2036年( 2027年~ 段階的に運用開始) 主要な 施設名称 ラ グビー場棟 複合棟A 複合棟B 公益施設 TEPIA (既存建物) 文化交流施設棟 野球場 球場併設ホテル棟 事務所棟 絵画館前 テニス場棟 敷地面積 約43,480㎡ 約12,100㎡ 約14,710㎡ 約6,080㎡ 約8,760㎡ 約69,040㎡ 約13,170㎡ 約40,550㎡ 計画容積率 150% 900% 200% - 150% 150% 1150% 200% 延床面積 約76,700㎡ 約127,300㎡ 約30,300㎡ - 約2,000㎡ 約115,700㎡ 約213,000㎡ 約15,300㎡ 頂部建物高さ 約55m 約185m 約80m - 約6m 約60m 約190m 約15m 用途 ラ グビー場 文化交流施設 店舗 駐車場等 オフ ィ ス 商業 駐車場等 スポーツ関連施設 宿泊施設 駐車場等 - 公園支援施設 商業等 野球場 宿泊施設 商業 駐車場等 オフ ィ ス 商業 駐車場等 テニス場 駐車場等 東京体育館 三井ガーデンホテル 国立競技場 聖徳記念絵画館 絵画館前 広場 文化交流施設棟 ( つなぎスポッ ト ) ラ グビー場棟 複合棟B TEPIA ( 既存建物) 複合棟A 野球場/ 球場併設ホテル棟 保全緑地 事務所棟 青山 OMスク エア 中央 広場 新宿区 港区 渋谷区 外苑東通り いち ょ う 並木 絵画館前 テニス場棟 スケート 場 御観兵榎 外苑キャ ン パス にこ にこ パーク 地区計画の区域 促進区の整備計画を進める区域 公園まちづく り 計画の区域 街区境界 敷地境界 区界 ■計画概要 ■配置図 ■位置図 ■イ メ ージパース( 東側から 計画地を望む) 国立競技場 秩父宮 ラ グビー場 伊藤忠商事 東京本社ビル 青山 OM スク エア 聖徳記念絵画館 東京体育館 神宮球場 第二球場 明治神宮外苑 テニスク ラ ブ 軟式野球場 テピア JSCテニス場 JAPAN SPORT OLYM PIC SQUARE 日本青年館・ 日本スポーツ 振興ビ ル THE COURT 神宮外苑 JR千駄ヶ 谷駅 JR信濃町駅 東京メ ト ロ・ 都営大江戸線 青山一丁目駅 東京メ ト ロ 外苑前駅 都営大江戸線 国立競技場駅 公益施設 市街地再開発事業予定区域
- 15. 地区計画の概要① 公共施設: 狭くなる建国記念文庫の森・絵画館前広場 令和3年7月21日 (港区)建設常任委員会 資料No.1、p.1.
- 16. 地区計画の概要②:建築規制:公園区域から外した地区に公園区域内の未利用容積を移転集約して超高層化 250% 450% 450% 150% 200% 900% 1150% 150% 200% 50% 令和3年7月21日 (港区)建設常任委員会 資料No.1、p.2. に大方が指定容積率を加筆 「容積率適正再配分型地区計画」
- 17. 計画の問題点
- 18. 地区計画の概要②:建築規制:公園区域から外した地区に公園区域内の未利用容積を移転集約して超高層化 250% 450% 450% 150% 200% 900% 1150% 150% 200% 50% 令和3年7月21日 (港区)建設常任委員会 資料No.1、p.2. に大方が指定容積率を加筆 空間デザイン上の問題点: ★緑とオープンスペースに関する問題: ①建国記念文庫の森の破壊 ②ラグビー場前の銀杏並木の滅失 ③4列の銀杏並木の枯損リスク ④絵画館前広場の囲い込み。 ★⑤容積移転を受けて建つ、突出した高さの超 高層ビル開発による景観や住環境の悪化 ★⑥歴史的建造物である神宮球場やラグビー場の 解体・滅失 「容積率適正再配分型地区計画」
- 22. オープンスペース面積算定についての疑問 「絵画館前広場としてオープンスペース約2.5ha新設」 というのは本当か? 22 [出典:事業者HP中の資料:< https://www.jingugaienmachidukuri.jp/green/> ] ここは実際にはオープンスペース 新設とはいえない。オープンスペースの面積はむしろ減っている。
- 26. 地区計画の概要②:建築規制:公園区域から外した地区に公園区域内の未利用容積を移転集約して超高層化 250% 450% 450% 150% 200% 900% 1150% 150% 200% 50% 令和3年7月21日 (港区)建設常任委員会 資料No.1、p.2. に大方が指定容積率を加筆 空間デザイン上の問題点: ★緑とオープンスペースに関する問題: ①建国記念文庫の森の破壊 ②ラグビー場前の銀杏並木の喪失 ③4列の銀杏並木の枯損 ④絵画館前広場の囲い込み。 ★容積移転を受けて建つ、突出した高さの超高層 ビル開発による景観や住環境の悪化 ★歴史的建造物である神宮球場やラグビー場の 解体・滅失 「容積率適正再配分型地区計画」
- 27. 特定緩和制度運用の問題:公園まちづくり制度について 27 [出典:東京都HP < https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kiban/kouen_2.htm> ] <「公園まちづくり制度」活用のイメージ> 2022/04/04 14:33 両立する新たな仕組み」 について基本方針と 実施要綱を定めまし た | 東京都都市整備局 案を基本と し ます。 行う ため、 審査会を 設置し ます。 https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kiban/kouen_2.htm ○ 制度の運用 ・ 民間事業者による提案を 基本と し ます。 ・ 公平・ 公正な審査を行う ため、 審査会を設置し ます。 ・ 必要に応じ て、 基本計画・ 都市計画等の変更( 都市計画公園の廃止、 再開発等促進区を 定める地区計画等) を行います • 民間事業者による提案を基本とします。 • 公平・公正な審査を行うため、審査会を設置します。 • 必要に応じて、基本計画・都市計画等の変更(都市計画公園の廃止、再開発等促 進区を定める地区計画等)を行います。
- 28. 28 ★ 「公園まちづくり制度」とは: (おおむね50年以上前に)都市計画公園として指定されたまま用地買収が進まず、実態として低層 密集市街地となっているような都市計画公園区域内の「未供用区域(2ha以上)」について、 これを都市計画公園区域から外して、 周辺も含めた地域に「再開発等促進区を定める地区計画」を定め、 一定規模以上の緑地(民間敷地の60パーセント以上かつ1.0ヘクタール以上)を地区施設等として確 保し、 「地域特性に応じた公園機能の発現と緑のネットワークの形成」を図ろうという制度。 ★ 神宮外苑の場合、ラグビー場の敷地が「主たる未供用区域」: しかし、ラグビー場の敷地は、広いまとまった敷地であり、JSC所有地=国有地。そこに不燃建築で あるラグビー場が建っているのであるから、(神宮球場と同様)そのまま公園施設としていい敷地 である。 にもかかわらず、施設の敷地が塀と門で囲われていて、市民に公開されていないというだけのこと で未供用区域扱いになっている。 この地区は、密集市街地とはいえず、再開発によって不燃化したり有効空地を整備したりする必要 の全くない地区。 しかも未供用区域に建っていたラグビー場を、都市計画公園区域内に移転・新設する計画になって いる。 このように、今のラグビー場の敷地を「未供用区域」として扱い、「公園まちづくり制度」を適用する のは、本来の「公園まちづくり制度」の主旨からは大きく外れている。 特定緩和制度運用の問題:公園まちづくり制度について
- 29. 250% 450% 450% 150% 200% 900% 1150% 150% 200% 50% 令和3年7月21日 (港区)建設常任委員会 資料No.1、p.2. に大方が指定容積率を加筆 特定緩和制度運用の問題:容積移転について 「容積率適正再配分型地区計画」
- 30. 特定緩和制度運用の問題:容積移転について 30 ★ この場所は、都市計画公園区域なので、公園施設として都知事の許可を受けた建物(および、解体や 移築の容易な木造や軽量鉄骨等の2階建ての建物)しか建てられない場所であって、土地所有者が「用 途地域」による指定容積率(200%)の範囲内であれば自由に建築できるという場所ではない。 • => (公園区域にかかっている用途地域の指定容積率が200%だからといって)明治神宮やJSC等の公 園区域内の土地の所有者が、容積率200%の開発権を「当然に可能な開発の権利」として持ってい るとはいえない場所である。 • 都市計画法や建築基準法では、都市計画公園区域内であっても、地区計画の区域内で容積を移転す る「容積適正配分型地区計画」を定めてはいけないという規定はないので、今回の容積移転が直ち に違法とはいえないが、適切な地区計画の使い方といえるのか? • この点について、都市計画審議会では、きちんと説明されていない。 ★ 容積移転制度とは(もともとはアメリカで始まった制度であるが)本来、緑地や歴史的建造物を、開 発や再開発から守り、保全するため、その敷地の未利用容積(=未利用開発権)を隣接地や遠く離れた 都心部などの建築敷地に売却して、そちらの敷地に上乗せして使うことを認めて、(開発や再開発させ ないことに対する)補償の代わりとする仕組み。 • 神宮外苑の場合でも、神宮球場やラグビー場を歴史的建造物として保全したり、建国文庫の森を保 全するために容積移転制度を使うのであれば、本来の使い方といえるが、歴史のあるラグビー場や 神宮球場を取り壊し、建国記念文庫の森や、ラグビー場前の銀杏並木、(さらには市街地再開発事 業区域の外の絵画館前広場の緑などの)樹齢百年超の多数の樹木を伐って、建物や施設を新設する 事業であるにもかかわらず、使わずに余った容積を超高層オフィスビル開発の敷地に移転して、そ ちらで使うというのは、適切な地区計画の使い方といえるのか?
- 31. まとめ:神宮外苑再開発の都市計画に関する問題群 1. 空間デザイン上の問題: a. 歴史的建造物といえる野球場・ラグビー場の建築が解体されてしまうこと。 b. ラグビー場と野球場を不整形な敷地に無理に押し込もうとするため、 ①建国文庫の森、②絵画館前広場、③ラグビー場前銀杏並木、④4列の銀杏並木 が毀損されること 2. 特定緩和制度運用上の問題: a. 公園まちづくり制度は、実態として密集市街地になってしまった都市計画公園区域内の未供用区域を、公 園区域からはずして、面的に再開発することを通じて、地区施設等としてまとまった緑地を確保し、公園 を代替するような地区にしようとする制度であるのに、神宮外苑地区では、現にラグビー場が建っている まとまった敷地を対象として、公園まちづくり制度を適用するのは、制度の本来の目的から逸脱している こと。 b. 建築が許可制になっていて、用途地域による指定容積率を開発権として土地所有者が所有しているとはい えない都市計画公園区域内の土地について、容積率適正配分型地区計画によって容積移転を行うことは、 地区計画の使い方として不適切なのではないか。また、神宮球場やラグビー場を歴史的建造物として保全 したり、建国文庫の森を保全するために容積移転制度を使うのであれば、本来の目的に沿った使い方とい えるが、歴史のあるラグビー場や神宮球場を取り壊し、建国記念文庫の森や、ラグビー場前の銀杏並木、 (さらには市街地再開発事業区域の外の絵画館前広場の緑などの)樹齢百年超の多数の樹木を伐って、建 物や施設を新設する事業であるにもかかわらず、都市計画公園区域内の使わずに余った容積を超高層オフ ィスビル開発の敷地に移転して、そちらで使うというのは、地区計画の使い方として不適切なのではない か。 c. 公園まちづくり計画の審議の過程で、事業者による説明会が行われたとはいえ、それ以外の市民参加の機 会が十分に確保されたとはいえないこと。 d. 地区計画の審議が、建築計画や樹木の扱いの詳細が決まっていない段階で、環境アセスメントに先行して 行われ、緑の保全の問題や、景観阻害の問題、さらに縦覧の際に多数提出された反対意見書について、審 議会で十分検討されないまま、公園まちづくり計画を丸呑みする形で、拙速に終結されたこと。
- 32. 計画案の変遷
- 33. 主な経緯:2018年3月 「確認書」まで https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/bosai/toshi_saisei/saisei07.htm などから作成 年月日 事項 2010年12月 「10年後の東京」への実行プログラム2011策定 :霞ヶ丘競技場一帯は、神宮スポーツクラスターとして、特区制度の活用などにより 整備された都市像を提示 2011年12月 「2020年の東京」計画策定(四大スポーツクラスターの整備):四大スポーツクラスターの一つとして、神宮地区を位置づけ。 2012年5月 森会長にラグビー場と野球場を入れ替える案を説明 2013年6月 神宮外苑地区地区計画の決定・都市計画公園明治公園の変更: 立体都市計画公園制度を活用して、都市計画公園区域を再編 2013年12月 「公園まちづくり制度」創設:・センター・コア・エリア内の都市計画決定から長期間(50年以上)経過した公園・緑地(未供用区域の面 積が2.0ヘクタール以上のもの)の一部を廃止又は変更し、これにかえて、周辺も含めた地域に(再開発等促進区を定める)地区計 画を定 め、一定規模以上の緑地(民間敷地の60パーセント以上かつ1.0ヘクタール以上)を地区施設等として確保する制度。 2014年7月 サブトラックを断念、スポーツ関連施設、事務所ビル等を組み込む案 2015年3月 「容積率の適正再配分」の文言が示された計画案を舛添知事に説明 2015年4月 神宮外苑地区まちづくりに係る基本覚書を締結:b区域(概ね今回の市街地再開発事業区域)について都と関係権利者間で覚書を 締結:公園まちづくり制度や市街地再開発事業の活用を想定 2016年7月 神宮外苑地区(b区域)まちづくり基本計画の検討に関する合意書を締結: 競技の継続に配慮しながらまちづくりを進めるため、ラグ ビー場・野球場を入れ替える素案を定めた 2016年10月 神宮外苑地区地区計画の決定・都市計画公園明治公園の変更: 地区施設(区画道路、歩行者通路、広場、緑道等)の追加・変更、 都市計画公園の区域を変更 2016年12月 --新国立競技場着工 2017年3月 神宮外苑地区地区計画の変更: 既存樹木をいかして、緑豊かなオープンスペース等の整備を図るとともに、にぎわいを創出する宿 泊・交流施設等の諸機能の導入を図る 2017年11月 都市計画公園明治公園の変更: 都市計画公園の立体的な範囲の一部を変更 2018年3月 神宮外苑地区(b区域)まちづくりの検討に係る今後の取組等に関する確認書取り交わし: -- (第2条) 関係者は、スポーツ施設の整備に加え、多様な用途の導入や緑の創出など、区域全体での一体的な再整備を目指し、 公園まちづくり制度や市街地再開発事業の活用も想定して検討を進める。
- 37. 主な経緯:2018年3月 「確認書」まで https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/bosai/toshi_saisei/saisei07.htm などから作成 年月日 事項 2010年12月 「10年後の東京」への実行プログラム2011策定 :霞ヶ丘競技場一帯は、神宮スポーツクラスターとして、特区制度の活用などにより 整備された都市像を提示 2011年12月 「2020年の東京」計画策定(四大スポーツクラスターの整備):四大スポーツクラスターの一つとして、神宮地区を位置づけ。 2012年5月 森会長にラグビー場と野球場を入れ替える案を説明 2013年6月 神宮外苑地区地区計画の決定・都市計画公園明治公園の変更: 立体都市計画公園制度を活用して、都市計画公園区域を再編 2013年12月 「公園まちづくり制度」創設:・センター・コア・エリア内の都市計画決定から長期間(50年以上)経過した公園・緑地(未供用区域の面 積が2.0ヘクタール以上のもの)の一部を廃止又は変更し、これにかえて、周辺も含めた地域に(再開発等促進区を定める)地区計 画を定 め、一定規模以上の緑地(民間敷地の60パーセント以上かつ1.0ヘクタール以上)を地区施設等として確保する制度。 2014年7月 サブトラックを断念、スポーツ関連施設、事務所ビル等を組み込む案 2015年3月 「容積率の適正再配分」の文言が示された計画案を舛添知事に説明 2015年4月 神宮外苑地区まちづくりに係る基本覚書を締結:b区域(概ね今回の市街地再開発事業区域)について都と関係権利者間で覚書を 締結:公園まちづくり制度や市街地再開発事業の活用を想定 2016年7月 神宮外苑地区(b区域)まちづくり基本計画の検討に関する合意書を締結: 競技の継続に配慮しながらまちづくりを進めるため、ラグ ビー場・野球場を入れ替える素案を定めた 2016年10月 神宮外苑地区地区計画の決定・都市計画公園明治公園の変更: 地区施設(区画道路、歩行者通路、広場、緑道等)の追加・変更、 都市計画公園の区域を変更 2016年12月 --新国立競技場着工 2017年3月 神宮外苑地区地区計画の変更: 既存樹木をいかして、緑豊かなオープンスペース等の整備を図るとともに、にぎわいを創出する宿 泊・交流施設等の諸機能の導入を図る 2017年11月 都市計画公園明治公園の変更: 都市計画公園の立体的な範囲の一部を変更 2018年3月 神宮外苑地区(b区域)まちづくりの検討に係る今後の取組等に関する確認書取り交わし: -- (第2条) 関係者は、スポーツ施設の整備に加え、多様な用途の導入や緑の創出など、区域全体での一体的な再整備を目指し、 公園まちづくり制度や市街地再開発事業の活用も想定して検討を進める。
- 39. 主な経緯:2018年3月 「確認書」まで https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/bosai/toshi_saisei/saisei07.htm などから作成 年月日 事項 2010年12月 「10年後の東京」への実行プログラム2011策定 :霞ヶ丘競技場一帯は、神宮スポーツクラスターとして、特区制度の活用などにより 整備された都市像を提示 2011年12月 「2020年の東京」計画策定(四大スポーツクラスターの整備):四大スポーツクラスターの一つとして、神宮地区を位置づけ。 2012年5月 森会長にラグビー場と野球場を入れ替える案を説明 2013年6月 神宮外苑地区地区計画の決定・都市計画公園明治公園の変更: 立体都市計画公園制度を活用して、都市計画公園区域を再編 2013年12月 「公園まちづくり制度」創設:・センター・コア・エリア内の都市計画決定から長期間(50年以上)経過した公園・緑地(未供用区域の面 積が2.0ヘクタール以上のもの)の一部を廃止又は変更し、これにかえて、周辺も含めた地域に(再開発等促進区を定める)地区計 画を定 め、一定規模以上の緑地(民間敷地の60パーセント以上かつ1.0ヘクタール以上)を地区施設等として確保する制度。 2014年7月 サブトラックを断念、スポーツ関連施設、事務所ビル等を組み込む案 2015年3月 「容積率の適正再配分」の文言が示された計画案を舛添知事に説明 2015年4月 神宮外苑地区まちづくりに係る基本覚書を締結:b区域(概ね今回の市街地再開発事業区域)について都と関係権利者間で覚書を 締結:公園まちづくり制度や市街地再開発事業の活用を想定 2016年7月 神宮外苑地区(b区域)まちづくり基本計画の検討に関する合意書を締結: 競技の継続に配慮しながらまちづくりを進めるため、ラグ ビー場・野球場を入れ替える素案を定めた 2016年10月 神宮外苑地区地区計画の決定・都市計画公園明治公園の変更: 地区施設(区画道路、歩行者通路、広場、緑道等)の追加・変更、 都市計画公園の区域を変更 2016年12月 --新国立競技場着工 2017年3月 神宮外苑地区地区計画の変更: 既存樹木をいかして、緑豊かなオープンスペース等の整備を図るとともに、にぎわいを創出する宿 泊・交流施設等の諸機能の導入を図る 2017年11月 都市計画公園明治公園の変更: 都市計画公園の立体的な範囲の一部を変更 2018年3月 神宮外苑地区(b区域)まちづくりの検討に係る今後の取組等に関する確認書取り交わし: -- (第2条) 関係者は、スポーツ施設の整備に加え、多様な用途の導入や緑の創出など、区域全体での一体的な再整備を目指し、 公園まちづくり制度や市街地再開発事業の活用も想定して検討を進める。
- 40. 主な経緯:2018年4月「まちづくり検討会」設置・以降 年月日 事項 2018年4月 「東京2020大会後の神宮外苑地区のまちづくり検討会」(委員:学識3名+関係3区の部長、都の担当3部長)を設置 (5月・7月・8月・10月) 4回の検討会を開催 8月31日〜9月29日 パブコメ実施 2018年 11月 「東京2020大会後の神宮外苑地区のまちづくり指針」を策定 2019年4月 -- JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE(日本スポーツ協会新会館)竣工 2019年11月 -- 三井ガーデンホテル神宮外苑の杜プレミア開業 2019年11月 -- 新国立競技場竣工 2020年1月23日・26日 事業者が「東京都公園まちづくり制度実施要綱」に基づく「神宮外苑地区公園まちづくり計画に関する説明会」を開催 (事業者)三井不動産株式会社(事業者代表)・宗教法人明治神宮・独立行政法人日本スポーツ振興センター・伊藤忠 商事株式会社 2020年2月7日 事業者が、東京都公園まちづくり制度実施要綱第4の1に基づく公園まちづくり計画の提案書を提出 2020年2月19日 上記提案書を収受し、「東京都公園まちづくり制度実施要綱」第5の1に基づき、検討会、専門部会及び審査会を設置 2020年3月3日 東京都公園まちづくり計画検討会(都市整備局技監を座長とする課長級職員の会議体) 2020年3月19日・6月2日 東京都公園まちづくり計画専門部会(学識3名(緑地・土木・建築)と都市づくり政策部の部長・課長からなる7名の会議 体) 2021年5月10日 事業者が、「東京都公園まちづくり制度実施要綱」第4の1に基づく公園まちづくり計画の一部変更を提出、同日収受 2021年5月14日 東京都公園まちづくり計画検討会 2021年5月21日 東京都公園まちづくり計画専門部会 2021年6月4日・5日・7日 事業者が「東京都公園まちづくり制度実施要綱」に基づく「神宮外苑地区公園まちづくり計画に関する説明会」を開催 2021年6月10日 東京都公園まちづくり計画審査会(都市整備局長を会長とする部長級職員の会議体) 2021年7月5日 事業者に対し、「東京都公園まちづくり制度実施要綱」第5の2(1)アに基づき、公園まちづくり制度を適用する旨を通知 2022年3月 神宮外苑地区地区計画の変更・都市計画公園明治公園の変更
- 41. 東京2020大会後の神宮外苑地区のまちづくり指針<素案>(案):(第3回検討会資料) 2018年8月 この図は最終的な「まちづくり指針」でも変わっていない。 ・野球場とラグビー場の位置を入れ替えることはぼかされているが、円の大きさでどちらが野球場かは分かる。 ・「4列のいちょう並木の保全」が明記され、野球場を示す円は銀杏並木から離れている。 ・建国記念文庫の緑には、ラグビー場を示す円は被さっていない。 ・絵画館前広場の両サイドには、スポーツ・文化交流機能と書かれているだけで、プライベートなテニスクラブに専有されるイメー ジは無い。 ・併せて「公園まちづくり制度」の活用要件も示されている。 41 <https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/bosai/toshi_saisei/data/jinguu_shishin01_06.pdf> スポーツ環境及びみどり と オープン スペースの方針図 大規模 スポーツ施設 新国立競技場 聖徳記念絵画館 外苑前駅 東京体育館 千駄ヶ 谷駅 信濃町駅 立体的に 確保さ れる 公園 ・ 連鎖的な建替え、 スポーツ 施設の歴史の継承 ・ 誰も が親し める環境整備・ スポーツ文化の発信 大規模 スポーツ施設 ・ いちょ う 並木から の眺望の保全 ・ 聖徳記念絵画館の前景と し て憩いの広場を創出 ・ 聖徳記念絵画館へのビス タ 景の周囲や背景の緑に より 、 より 風格のある空 間を 形成 ・ 青山通り 側の地区の顔と し て、 ゲート 性のある オープンスペースを形成 ・ 青山ら し い気品と にぎわ いと 憩いのある歩行者空 間と 、 まと まり のある緑 の確保 ・ 多目的に利用可能なフ リ ー スペースと し て、 地区の中 心と なるまと まっ た開かれ た広場空間を確保 ・ スポーツ施設と 広場、 広場 と 広場等の相互の連携が可 能で多く の人々が行き交う 場所、 開放的な空間を整備 ・ 2 つの広場を つな ぐ 機能・ 空間整備 広場 ( 既定) 国立 競技場駅 広場( 既定) だ 溜 • 道路沿いやオープンスペースへの高木の植栽により 、 印象的な並木環境を創出・ 充 実 • スポーツ施設の周辺には、 人溜まり 空間の確保に配慮し た広場状のオープンスペー スを配置すると と も に、 芝生や高木等により 、 歩行者動線と も 連携し た緑化を行う 。 • 緑地等と し て整備さ れるデッ キ等は、 イ ベント 時の大量の歩行者流動をさ ばく も の と し てだけではなく 、 イ ベント のないと き には、 憩い、 滞在できる有効な空間と し て整備 • 建物の壁面や屋上、 デッ キ上等における立体的な緑化 • 歩行者動線やジョ ギングコ ースへの緑陰空間の形成など、 スポーツ環境への配慮 • 憩い・ 安ら ぐ 場所と し ての緑陰空間を創出 • 生物多様性や外苑の歴史、 四季の彩り に配慮し た樹種の植栽 • 従来より も 緑量を増加
- 42. 主な経緯:2018年4月「まちづくり検討会」設置・以降 年月日 事項 2018年4月 「東京2020大会後の神宮外苑地区のまちづくり検討会」(委員:学識3名+関係3区の部長、都の担当3部長)を設置 (5月・7月・8月・10月) 4回の検討会を開催 8月31日〜9月29日 パブコメ実施 2018年 11月 「東京2020大会後の神宮外苑地区のまちづくり指針」を策定 2019年4月 -- JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE(日本スポーツ協会新会館)竣工 2019年11月 -- 三井ガーデンホテル神宮外苑の杜プレミア開業 2019年11月 -- 新国立競技場竣工 2020年1月23日・26日 事業者が「東京都公園まちづくり制度実施要綱」に基づく「神宮外苑地区公園まちづくり計画に関する説明会」を開催 (事業者)三井不動産株式会社(事業者代表)・宗教法人明治神宮・独立行政法人日本スポーツ振興センター・伊藤忠 商事株式会社 2020年2月7日 事業者が、東京都公園まちづくり制度実施要綱第4の1に基づく公園まちづくり計画の提案書を提出 2020年2月19日 上記提案書を収受し、「東京都公園まちづくり制度実施要綱」第5の1に基づき、検討会、専門部会及び審査会を設置 2020年3月3日 東京都公園まちづくり計画検討会(都市整備局技監を座長とする課長級職員の会議体) 2020年3月19日・6月2日 東京都公園まちづくり計画専門部会(学識3名(緑地・土木・建築)と都市づくり政策部の部長・課長からなる7名の会議 体) 2021年5月10日 事業者が、「東京都公園まちづくり制度実施要綱」第4の1に基づく公園まちづくり計画の一部変更を提出、同日収受 2021年5月14日 東京都公園まちづくり計画検討会 2021年5月21日 東京都公園まちづくり計画専門部会 2021年6月4日・5日・7日 事業者が「東京都公園まちづくり制度実施要綱」に基づく「神宮外苑地区公園まちづくり計画に関する説明会」を開催 2021年6月10日 東京都公園まちづくり計画審査会(都市整備局長を会長とする部長級職員の会議体) 2021年7月5日 事業者に対し、「東京都公園まちづくり制度実施要綱」第5の2(1)アに基づき、公園まちづくり制度を適用する旨を通知 2022年3月 神宮外苑地区地区計画の変更・都市計画公園明治公園の変更
- 43. 結論と提言
- 44. 結論と提言 現計画は神宮外苑地区の緑の量と質を大幅に劣化させ、歴史的建造物を滅失さ せ、神宮外苑地区を遊園地のような空間に変えるもの 現在の神宮外苑再開発計画とは: ① 「公園まちづくり制度」を使って、スタジアム通り沿いの土地の一部を公園区 域からはずし、 ② 「再開発促進区を定める地区計画と容積率適正配分型地区計画」を使って、公 園区域からはずした土地や公園の南に隣接する伊藤忠本社のある土地に、公園 内の余剰容積を移転集約して超高層ビル等を建て、 ③ その利益を活用して、屋根付きラグビー場を今の第2球場と建国記念文庫の森 のところに新築し、 ④ ラグビー場の跡地に新しい神宮球場を新築し、 ⑤ 新神宮球場に追い出された会員制テニスコートを絵画館前広場に移設する、と いうもの。 しかし、スタジアム通り沿いの土地を公園からはずした残りの不整形な狭い 敷地の中で、4列の銀杏並木を傷めないような位置に、野球場を納めること は困難。 ラグビー場の移転新築で建国記念文庫の森を潰すことも大問題。 再開発事業区域外の絵画館前広場はテニスコートで専有されてしまう。 地区全体の建築計画の抜本的な変更が必要。
- 45. 結論と提言 どうすべきか 競技を継続しながら、ラグビー場も野球場を建て替え、その費用を、容 積移転を受けた超高層ビル開発の利益で捻出する、という虫の良い話 は、神宮外苑の緑やオープンスペースを劣化させない限り不可能。とい うことが明らかになってきたのが、現在の状況。 容積割り増しで、土地の高度利用を進めて、都民・国民の共通資産であ り、東京の大きな魅力の一つでもある、百年以上の歴史のある貴重な緑 豊かな空間と、築50年を超える歴史的建造物を潰して、ピカピカのオフ ィス街・歓楽街や遊園地のようなものを作るというのは、先人がつくり 育て護ってきた、将来の世代に受け継いでいくべき、かけがえのないも のを失う、まことに愚かなこと。 歴史的建造物である、神宮球場とラグビー場は、今の建物をリノベーシ ョン(大幅改修)して、バリアフリー化などを進めつつ、保全すれば、 緑やオープンスペースをほとんど損なうことなく、施設を近代化するこ とができる。改修なので、費用もさほどかからない。
- 46. 結論と提言 流れは変えられる 公園区域の変更や、地区計画は、既に都市計画決定済だが、都市計画というのは、 いつでも、どのようにでも、変更できるもの。 そもそも地区計画は、建てられる建物の用途・容積率・高さなどの限度を定めただ けのもの。 都市計画公園区域内では、木造2階建てなどの簡易なものを別にして、許可を受け た公園施設しか建てられない。 都の当局がアセスの状況や市民の意見を踏まえて、当分、許可を下ろさなければ ラグビー場などの建物を建築することはできない。 しかも、市街地再開発事業の都市計画決定は、アセスメントの結果待ちで、手続き はこれから。 一連の都市計画決定・変更手続きは、最終段階のちょっと前のところに来てはいる けれど、まだ終わったわけではないこと。 このプロジェクトは、まだまだ、抜本的な見直し、全面的な取り下げの可能性があ るもの。 提言 神宮外苑地区の再整備計画は、神宮球場とラグビー場の現地改修保全 (リノベーション)を基本に据えたものに抜本的に変更すべきです。
- 47. 参考資料
- 49. 都市計画公園内で建築できるもの 都市計画法 第二節 都市計画施設等の区域内における建築等の規制 (建築の許可) 第五十三条 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする 者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次に掲 げる行為については、この限りでない。 一 政令で定める軽易な行為 二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為 三 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為 四 第十一条第三項後段の規定により離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度が定められている都市計 画施設の区域内において行う行為であつて、当該離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度に適合するも の 五 第十二条の十一に規定する道路(都市計画施設であるものに限る。)の区域のうち建築物等の敷地として 併せて利用すべき区域内において行う行為であつて、当該道路を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれが ないものとして政令で定めるもの 2 第五十二条の二第二項の規定は、前項の規定による許可について準用する。 3 第一項の規定は、第六十五条第一項に規定する告示があつた後は、当該告示に係る土地の区域内にお いては、適用しない。 都市計画法施行令 第二節 都市計画施設等の区域内における建築等の規制 (法第五十三条第一項第一号の政令で定める軽易な行為) 第三十七条 法第五十三条第一項第一号の政令で定める軽易な行為は、階数が二以下で、かつ、地階を有 しない木造の建築物の改築又は移転とする。
- 50. 都市計画公園内で建築できるもの 都市計画法 (許可の基準) 第五十四条 都道府県知事等は、前条第一項の規定による許可の申請があつた場合において、当該申請 が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可をしなければならない。 一 当該建築が、都市計画施設又は市街地開発事業に関する都市計画のうち建築物について定めるものに 適合するものであること。 二 当該建築が、第十一条第三項の規定により都市計画施設の区域について都市施設を整備する立体的な 範囲が定められている場合において、当該立体的な範囲外において行われ、かつ、当該都市計画施設を整 備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないと認められること。ただし、当該立体的な範囲が道路である都 市施設を整備するものとして空間について定められているときは、安全上、防火上及び衛生上支障がないも のとして政令で定める場合に限る。 三 当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認 められること。 イ 階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。 ロ 主要構造部(建築基準法第二条第五号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロ ツク造その他これらに類する構造であること。
- 51. 都市計画公園内で建築できるもの 都市公園法 第2条 第2項 この法律において「公園施設」とは、都市公園の効用を全うするため当該都市公園に設けら れる次に掲げる施設をいう。 一 園路及び広場 二 植栽、花壇、噴水その他の修景施設で政令で定めるもの 三 休憩所、ベンチその他の休養施設で政令で定めるもの 四 ぶらんこ、滑り台、砂場その他の遊戯施設で政令で定めるもの 五 野球場、陸上競技場、水泳プールその他の運動施設で政令で定めるもの 六 植物園、動物園、野外劇場その他の教養施設で政令で定めるもの 七 飲食店、売店、駐車場、便所その他の便益施設で政令で定めるもの 八 門、柵、管理事務所その他の管理施設で政令で定めるもの 九 前各号に掲げるもののほか、都市公園の効用を全うする施設で政令で定めるもの 同施行令 第5条 第4項 法第二条第二項第五号の政令で定める運動施設は、次に掲げるものとする。 一 野球場、陸上競技場、サッカー場、ラグビー場、テニスコート、バスケットボール場、バレーボール場、ゴ ルフ場、ゲートボール場、水泳プール、温水利用型健康運動施設、ボート場、スケート場、スキー場、相撲 場、弓場、乗馬場、鉄棒、つり輪、リハビリテーション用運動施設その他これらに類するもの及びこれらに附 属する観覧席、更衣所、控室、運動用具倉庫、シャワーその他これらに類する工作物 二 前号に掲げるもののほか、都市公園ごとに、地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては当該地方 公共団体が条例で定める運動施設、国の設置に係る都市公園にあつては国土交通大臣が定める運動施設
Notes de l'éditeur
- 皆様、こんにちは。ご紹介にあずかりました「大方潤一郎」です。都市計画を専門とする大学の教師を40年ほど務めてきたところです。
- さて、早速ですが、本日のセミナーのテーマは、神宮外苑再開発を推進するための「都市計画」についての問題を検討しようということです。 ひとくちに、都市計画に関わる問題といっても、問題には2つの側面があります。 ①第1に、公園を含む外苑地区の施設再整備計画が、公園や市街地のデザインとして妥当なのか、という都市空間のデザインに関する問題。 ②第2に、そのデザインを実現するため、「公園まちづくり制度」と「地区計画」を使って、現状の土地利用規制や建築規制を緩めているわけですが、こうした特定緩和型都市計画制度の使い方(つまり規制緩和の仕方や程度)が制度の本来の目的に即しているのかという問題、および、公園まちづくり計画や地区計画の決定に至る審議の過程がフェアで適正なものであったのか、(つまり意志決定過程が透明で民主的なものとなっているのか、客観的・科学的な審議がつくされ、市民の意見を反映させる機会が十分に用意され、市民共有の環境資産を損ない、特定の者だけが不当な利益を享受するような計画になっていないか)という問題です。 神宮外苑再開発に関する都市計画の場合、これらの2つの面で多くの問題があって、 しかも、この2つの問題が複雑に絡み合っているため、なかなかスッキリとした説明が難しいのですが、 なんとか、分かりやすく事態を読み解いてみたいと思います。
- さて、今、計画されている神宮外苑再開発とは、どんなプロジェクトなのでしょう。 まず、そこは、どんな場所なのでしょうか?
- 神宮外苑地区には、広く、地区計画がかかっておりますが、地区計画がかかっている範囲の中の土地・建物の所有状況を示したものがこの図です。 緑のところが、宗教法人明治神宮の所有地、薄茶色がJSC(独立行政法人・日本スポーツセンター)の土地、紫の(東京体育館や、もと都営住宅があって今は明治公園になっているところ)が東京都の所有地、その他、伊藤忠本社のある赤い土地、その隣の青い日本オラクル等の土地、紺色の一般財団法人高度技術社会推進協会(TEPIA)の土地、黄色の民間マンションの外苑ハウスの土地などがあります。
- で、この地区計画がかかっている区域のうち、図のように、赤い破線で囲まれた区域が都市計画で公園として指定されている区域です。 都市計画公園というのは、都市計画として公園にすると決めた場所のことで、この区域内では、土地が公有地でなく、自分の土地であっても、許可を受けなければ建築を建てることはできませんし、 木造や軽量鉄骨建ての2階建ての建物か、公園施設として建てるもの以外は、許可されません。 つまり、都市計画公園区域内では、民地であっても、マンションとかオフィスビルなどは建てられないのです。 なお、運動場、競技場や、美術館・博物館、動物園、宿泊施設(つまりホテル)などは、都市計画公園区域内であっても、公園施設として建てることができます。
- この場所にかかっている、地域地区を見ておきましょう。 まず、用途地域については、この図のように、青山通り沿いは商業地域(容積率700%〜600%)ですが、その他地区計画区域内は、大半が住居系地域で容積率は200%、ごく一部に300%、400%が指定されている場所があることが分かります。
- これは高度地区の指定状況です。都市計画公園区域内の大半は水色の第2種高度地区がかかっていますが、ラグビー場のところや商業地域は高度地区の指定がありません。 また、高度地区による高さ制限は、地区計画で別の定めをした場合は、地区計画による定めが優先されることになっています。
- これは、日影規制の指定状況です。再開発促進区として定めた地区計画の区域内では、日影規制を適用しないことにするのが一般的です。 ただし、その場合でも、地区計画の区域の外に落とす影については、影を落とす場所にかかっている日影規制が適用されます。
- さて、では、この場所を、どう変えようというのでしょうか。
- 今ある樹齢百年超の緑を潰しながら、いろいろな建物を建てて、この図にあるような、かなり建て込んだ空間に変えてしまおうというのが、「神宮外苑地区「公園まちづくり計画」による再整備計画」です。 「公園まちづくり計画」とは何かということについては、後で、詳しくお話しします。 ともあれ、今回、「公園まちづくり計画」によって、空間を大きく変えようとする区域は、図の赤い線で囲まれた区域です。(クリック) で、この「公園まちづくり計画」の区域が、今回、再開発促進区を含む地区整備計画を決めた区域でもあるわけです。
- また、今、環境アセスメントの対象になっていて、審議が継続中の「市街地再開発事業」の区域は、(クリック)この紺色の破線で囲まれた区域です。 「市街地再開発事業」を行う区域は、「公園まちづくり計画」の区域から、TEPIAの敷地と、絵画館前広場、および4列の銀杏並木の道路敷になっている部分を除いた区域になっていることに注意してください。
- で、このプロジェクトで、何をするかというと、具体的には… ①まず、今の神宮第二球場のところに屋根付きラグビー場を新設します。(ただしラグビー場は今の第二球場の敷地には納まらないので、その北にある大切な建国記念文庫の樹齢百年超の森を潰すことになります。) ②次に、ラグビー場を解体した跡地に神宮球場を新設します。野球場は、もとのラグビー場の敷地には収まらないので、明治神宮の所有地内にあるラグビー場前の銀杏並木を潰しながら③4列の銀杏並木の直近まで迫ることになります。 ④さらに、新しい野球場に押し出されたかっこうで明治神宮の会員制テニスコートが(再開発事業区域外の)絵画館前広場に移転します。 こうして、樹齢百年超の樹木が散在する誰でも自由に入って楽しめるパブリックなオープンスペースであった絵画館前広場の両サイドが、会員限定のプライベートな閉鎖的空間に変わり、パブリックなオープンスペースはストリート型の幅の狭い芝地だけになるわけです。
- これが、現在の神宮外苑の姿です。こうして空から俯瞰すると、意外にまとまった緑が少ないこと。建国記念文庫の森や、銀杏並木、および絵画館前広場の縁辺部にある緑が貴重であることが分かります。 また、開けたオープンスペースも意外に少なく、ラグビー場や野球場のグランド、テニスコートのグランドはかなり広く存在しますが、誰でも入って楽しめる、広いオープンスペースは絵画館前広場ぐらいしかないことが分かります。 ところが、今回のプロジェクトは、これらの貴重な、まとまった緑と、まとまったオープンスペースを台無しにしてしまうわけです。
- ⑤同時に、公園の西側のスタジアム通り沿いの土地(約3.4ha)を都市計画公園区域から外し(クリック)、そのうち市街地再開発事業を行う区域(つまり既にTEPIAのビルが建っている敷地を除いた区域)に、公園区域内の未利用容積を移転集約して、(公園区域内では建てられない)超高層オフィスビル等を「市街地再開発事業」によって開発します。 (その新しく建つオフィスビル等の床を「保留床」として処分することによって、明治神宮やJSCにとっては、「実質的にタダ同然の」費用負担でラグビー場と野球場を公園区域内に移転・新設することができるわけです。
- こうした突出した容積率と高さのオフィスビル等の開発を可能にするための、特定緩和型都市計画が「(再開発促進区を定める)地区計画」です。 この地区計画では、まず、この図のような公共施設の配置が定められています。 建国記念文庫の森や、絵画館前広場は、現状よりずっと小さくなることが分かります。
- 建築規制(特に建物の用途と容積率と高さ)については、この図のように設定されています。 この地区計画は、通常の再開発促進区を定める地区計画のように、有効空地の整備等の公共貢献に対する見返りとして容積割り増しを行うのではなく、 「容積率適正配分型地区計画」という手法を使って、 公園区域から外した土地の一部(図のA-8-c地区とA-9地区)に、 公園内の土地(具体的には、新ラグビー場と新神宮球場の敷地、および、4列の銀杏並木の東側および南側のわずかな緑地の区域=B-2地区)の「使わない容積」を移転して、 超高層ビルを建てる土地の容積率を大幅に緩和しているところに特徴があります。 こうして、この地区計画によって大幅に緩和された建築規制の枠内で、市街地再開発事業として、ラグビー場、野球場、およびオフィスビル、商業ビル等の開発を行い、 また市街地再開発事業区域の外にある、絵画館前広場での屋内テニス場・屋外テニス場の開発を行うことになるわけです。
- さて、では、この計画の問題点を、あらためて検討いたしましょう。
- こうして、ざっとプロジェクトの概要を眺めただけでも、 このプロジェクトには、いくつかの大きな問題点があることがわかります。 まず、緑とオープンスペースに関して、 ①建国記念文庫の樹齢百年超の森の破壊、 ②樹齢百年超のラグビー場前の銀杏並木の滅失 ③新神宮球場による4列の銀杏並木の枯損のリスク ④絵画館前広場の囲い込み の4つの問題があり、 さらに、⑤容積移転を受けて建つことになる、突出した高さの超高層ビル開発による、景観や住環境の悪化の問題があり、 さらには、そもそも、⑥歴史的建造物といえる神宮球場・ラグビー場の破壊による滅失、という大問題もあるわけです。
- このように、この事業では、建物の移設や新築によって、緑の質・量ともに劣化するわけですが、これに対し、事業者の作った「公園まちづくり計画」の提案書では、オフィスビルの足回りの緑化や屋上緑化、あるいは神宮球場移転後の跡地を緑地として整備することなどで、公園まちづくり区域内の「緑の割合」が25%から30%に増加するとしています。
- しかし、これは、芝地や屋上庭園なども含めて、樹木でなく、草やコケでも、とにかく地面や床に何か植物が載っていれば「緑地」と考え、一方、絵画館前広場のような、樹木に囲まれた芝地のオープンスペースの中であっても、一部、軟式野球場の内野のエリアなど、芝が生えていない、土がむき出しになっているところは緑地としてカウントしないという、一般市民の感覚とは、かなりズレた考え方によって算定した数字でしかありません。 芝生の広い広場があって、その一部の芝が踏まれて枯れていて土むき出しの部分がかなりあったとしても、その部分は緑地と認識するのが、一般市民の感覚ではないでしょうか。 ゴルフ場のバンカーは草が生えていないから緑地ではない、と屁理屈を捏ねるようなものでしょう。
- ですから、再開発によって緑地面積は増えているとはいえません。 まして、緑のボリューム、つまり樹木・草木の根や幹や枝や葉の体積または総重量という点では、古い大きな木が多数失われますから、大幅な減少になるわけです。
- また、オープンスペースの面積についても、事業者の示した図では、現在の軟式野球場のグランドをオープンスペースではないとして面積の測定から外していますが、(クリック)この場所は、誰でも、申し込めば、野球の試合や練習などに自由に使えるパブリックな緑地・広場になっているわけですし、野球場のグランド内に踏み込まなくても、回りから芝と土の広く開けた、かつ人々が野球をする風景が楽しめる、樹齢百年超の樹木に囲まれた、大きな緑の広場になっているわけです。 このように、事業者は、現在の軟式野球場のグランドをオープンスペースから外すことで、絵画館前広場の中央部分の芝地の広場(2.5ha)を「新設」したといって、テニスコートの移設によるオープンスペースの減少の影響を少なく見せようとしているわけですが、実際には、絵画館前広場に屋根付きのテニスコートの建物や、高いフェンスで囲まれたテニスコートが並ぶことで、絵画館前広場のオープンスペースの、視覚的・景観的・体感的な、拡がり感・開放感は、開発によって、大きく損なわれることは明らかです。
- もう一つの大問題は、なんといっても、4列の銀杏並木の保全の問題です。 これは、つまり、新しい神宮球場を建てる位置の問題です。 このプロジェクトの基本的な考え方は、ラグビー場を今の第2球場のところに移し、ラグビー場の跡地に新しい神宮球場を建てる、というものです。 このアイディアは(施設が使えなくなる期間がなくて)一見よさそうに見えたのでしょうが、 ラグビー場も野球場も、オフィスやマンションなどと違って建物の形や寸法が自由になりません。 その小さくしたり変則的な形にできないプロ野球の野球場を、(TEPIAが参加しないためきわめて不整形になっている)市街地再開発事業の区域に、納めることは、実際に野球場の建築の設計をしてみると、なかなか難しいのでしょう。 現在の計画では、野球場の外野席(ライト側)がかなり削られた、変則的な形状になっていますが、それでも、4列の銀杏並木の一番西側の銀杏と、その東にある銀杏の中間あたりにある道路(歩道)と敷地の境界線から、わずか8mのところに野球場の壁が立つ設計になっているわけです。 環境アセスメント審議会での事業者側の説明では、一番西側の銀杏の幹の中心からは6mということでした。これでは、一番西側の銀杏並木は、かなりのダメージを受けることになるのは明らかです。
- この左側の写真で、フェンスの建っているあたりに、深夜球場の壁が建つわけです。道路と敷地の境界線から8mのところなので、銀杏の幹の中心からだと6mぐらいのところになるわけです。
- 今年の夏の、環境アセスメント審議会で事業者が示した案では、この図のように、銀杏の根の状況を調査した上で、問題があれば、建物や基礎の作り方を微修正して「根系への影響を低減します」としていますが、 この程度の工法の変更では、確かに、少しは、根系への影響は低減するでしょうが、影響の低減はわずかですから、銀杏の健全性への大きな影響は避けられないでしょう。 このままでは、銀杏並木が枯損するリスクは、かなり大きいといわざるとえません。 野球場の外壁の位置を、銀杏の幹の中心から、十分に離すことが必要でしょう。 安全を見込むのであれば、15mは離して欲しいところです。 でも、そうすると、おそらく、今の不整形の狭い敷地では、ホテルを上に載せた野球場を納めるのは不可能なのではないでしょうか。 地区全体の建築計画の抜本的な変更が必要なのではないでしょうか。 そもそも、現に建っている歴史的建造物である、神宮球場とラグビー場は、今の建物をリノベーション(大幅改修)して、バリアフリー化などを進めつつ、保全すれば、緑やオープンスペースをほとんど損なうことなく、施設を近代化することができるわけです。 改修ですから、費用もさほどかかりません。
- もう一つの問題は、 オフィスビル等を建てる敷地を都市計画公園区域からはずし、 そこに、公園区域内のラグビー場、野球場の敷地や、4列の銀杏並木の入口付近や東側の緑地の土地の、「余っている」容積を移転・集約して、 突出した高さの超高層のオフィスビルを建てることです。 こうした超高層オフィスビル開発にともなう景観や住環境の悪化は、たいへん大きな問題なのですが、 この問題については、時間も限られておりますので、今日は深入りしないことにいたします。
- 次に、特定緩和制度の運用の問題についてです。 まず、公園まちづくり制度について。 そもそも、「公園まちづくり制度」とは、制度創設時の公式の説明によれば、 (おおむね50年以上前に)都市計画公園として指定されたまま用地買収が進まず、 実態として低層密集市街地となっているような、都市計画公園区域内の未供用区域(2ha以上)について、 これを都市計画公園区域から外して、周辺も含めた地域に「再開発等促進区を定める地区計画」を定め、 一定規模以上の緑地(民間敷地の60パーセント以上かつ1.0ヘクタール以上)を地区施設等として確保し、 「地域特性に応じた公園機能の発現と緑のネットワークの形成」を図ろうという制度です。
- 神宮外苑の場合、ラグビー場の敷地が「主たる未供用区域」とされていますが、ラグビー場の敷地は、広いまとまった敷地で、JSC所有地=つまり国有地であり、そこに不燃建築であるラグビー場が建っているわけで、神宮球場と同様、そのまま公園施設にしてもいいような施設であるにもかかわらず、施設の敷地が塀と門で囲われていて、市民に公開されていないというだけのことで未供用区域扱いになっているわけです。 この地区は、どう見ても、密集市街地とはいえず、再開発によって不燃化したり有効空地を整備したりする必要の全くない地区ですから、この「未供用区域」を主な対象として「公園まちづくり制度」を適用するのは、制度の本来の主旨からは大きく外れているといえます。 しかも事業者が提案した「公園まちづくり計画」を都として採択することは、その後の都市計画(公園計画の変更、再開発促進区を定める地区計画)の内容をほぼ固めてしまうことになるにもかかわらず、その内容の審議については、事業者による「説明会」は一応開催されたものの、都市計画決定の手続きほどの市民・住民の関与の機会(たとえば公聴会、縦覧・意見書)は用意されていません。 提案を審議する会議体についても、学識委員3名を含む専門部会が設置されたとはいえ、検討会・審査会は、都の職員のみで構成されていることも問題です。 「公園まちづくり計画」を詰めていく段階で、建築物や施設の設置による緑環境の劣化に関する問題をきちんと検討しておかなかったことが、事業着工前の最後の関門ともいえる、市街地再開発事業の環境アセスメント審議会の最後の段階で、データ不足、建築構法等の詳細の未決定が問題となって、足踏み状態になっているわけです。
- 最後に、【地区計画による容積移転の問題】についてです。 この地区計画は、「容積率適正配分型地区計画」という手法を使って、公園内の土地(具体的には、新ラグビー場と新神宮球場の敷地、および、4列の銀杏並木の東側および南側のわずかな緑地の区域=B-2地区)の「使わない容積」を、公園区域から外した土地の一部(図のA-8-c地区とA-9地区)に移転・集約して、その土地に超高層オフィスビルが建てられるようにしているところに特徴があります。 ですが、この容積移転が適切かどうかについても疑問があります。 というのも、ここは都市計画公園区域に指定された場所ですから、ここに指定されている用途地域による容積率規制(200%)の範囲内であれば自由に建築が出来るわけではなく、公園施設として都知事の許可を受けた建物(および、解体や移築の容易な木造や軽量鉄骨等の2階建ての建物)しか建てられない場所ですから、 宗教法人明治神宮やJSCなどの、土地所有者が、「当然に可能な開発の権利」として用途地域によって許容されている容積率200%の開発権を持っているとはいえない土地なのです。
- 都市計画法や建築基準法では、都市計画公園区域内であっても、地区計画の区域内で容積を移転する「容積適正配分型地区計画」を定めてはいけないという規定はないので、今回の容積移転が直ちに違法とはいえませんが、適切な地区計画の使い方なのかどうか、議論の余地のある話だと思えます。 が、そのことについても、都市計画審議会で説明されたり議論されたりした形跡は見当たりません。 そもそも、容積移転制度は、アメリカで始まった制度ですが、緑地や歴史的建造物を開発や再開発から守り保全するため、まだ使っていない容積(未利用容積=未利用開発権)を、隣接地や、遠く離れた都心部などの建築敷地に売ること認めて、開発や再開発を禁止することに対する公共による補償の代わりにする仕組みです。 ですから、神宮外苑の場合でも、神宮球場やラグビー場を歴史的建造物として保全したり、建国記念文庫の森を保全するために容積移転を使うのなら本来の使い方といえますが、 歴史的建造物を取り壊し、森を潰して再開発する事業を推進するために、公園区域内の見かけ上の余剰容積率を、超高層オフィスビル開発のために移転集約するというのは、容積移転制度の本来の目的から全く外れているわけで、これは、はたして適切な使い方といえるのか大いに疑問です。
- ということで、計画の問題点を、ここに要約しておきましたが、時間もないので、今は読み上げず、先に進みます。
- さて、では、どういう経緯で、こうした乱暴な再開発プロジェクトの計画が策定されてきたのでしょうか。
- 神宮外苑再開発計画に関する年表を作ってみました。 これを見ると、 東京都は、2012年頃から、ラグビー場と神宮球場の位置を入れ替えて再開発することの検討を始めていたようです。
- これは、2015年5月15日に、都の担当者が、森(元総理大臣)に示して説明したといわれている図です。 このプランでは、単純に、ラグビー場と神宮球場の位置を入れ替えるだけで、新築するオフィスビルやTEPIAのビル等は描かれていません。 第2球場と建国記念の森は新国立競技場のサブトラックになっています。
- その後、2014年7月10日の日付のある資料では、サブトラックの設置を断念し、ラグビー場を第2球場のところに移転・新設し、神宮球場の跡地には、スポーツ関連施設、事務所ビル等を設置する案に変わっています。現在の計画の基本的な考え方が現れています。
- さらに、2015年3月13日に、舛添知事に説明した再開発計画案では、公園まちづくり制度の活用/容積率の適正配分/絵画館前広場へのテニスコートの移設などが示されています。 この頃に現計画の骨子が、ほぼ固まったと思われます。
- さらに、今の案を念頭に置きながらと思われますが、2015年4月、都と関係地権者の間で「基本覚え書き」を締結しています。 (覚え書きでは、公園まちづくり制度や市街地再開発事業の活用することが書かれています)。 さらに、2016年7月:には、この基本覚え書きは、「合意書」に発展し、「競技の継続に配慮しながらまちづくりを進めるため、ラグビー場・野球場を入れ替える素案」が明示されるようになりました。
- これが「合意書」に示された、再整備構想の図です。 現在の施設配置構想がほぼ固まっているようです。
- そして、2018年3月には、都と関係地権者は、神宮外苑地区(b区域)の「まちづくりの検討に係る今後の取組等に関する確認書」を取り交わしています。 この確認書の(第2条)には「 関係者は、スポーツ施設の整備に加え、多様な用途の導入や緑の創出など、区域全体での一体的な再整備を目指し、公園まちづくり制度や市街地再開発事業の活用も想定して検討を進める。」ということが明記されています。 ここまでの間、こうした再開発の方針は、都と関係地権者の間で、ほぼ秘密裏に検討されてきたわけです。
- 検討が表だって進められるようになるのは、都と地権者の間での「確認書」が取り交わされた直後の、2018年4月からになります。 2018年4月に、「東京2020大会後の神宮外苑地区のまちづくり検討会」が設置されます。(この会の委員は、学識委員3名+関係3区の担当部長、都の担当3部長の計9名です。検討会は4回の検討会を開催し、8月31日~9月29日にはパブコメを実施し、 11月に「東京2020大会後の神宮外苑地区のまちづくり指針」が策定されています。
- 指針に示された開発構想は、 この図のような、漠然としたもので、建国記念文庫の森や4列の銀杏並木、絵画館前広場の緑に決定的なダメージを与えることが分かるような計画ではありませんでした。 この「指針」を受けて、事業者が、公園まちづくり計画を策定する中で、さきほど指摘したような、緑やオープンスペースに決定的なダメージを与えるような建築計画が描かれて行くわけです。 その意味では、事業者が提案した公園まちづくり計画は、この「東京2020大会後の神宮外苑地区のまちづくり指針」に反するものだといえるかもしれません。
- この「指針」に即して、関係地権者による事業者(三井不動産株式会社(事業者代表)・宗教法人明治神宮・独立行政法人日本スポーツ振興センター・伊藤忠商事株式会社)が、「神宮外苑地区公園まちづくり計画」の案を作成し、2020年1月に説明会を開催、その上で、2月に公園まちづくり計画の提案書を都に提出。都は、それを受けて、検討会、専門部会及び審査会を設置します。 事業者は、検討会、専門部会の意見を受けて、翌2021年5月10日に、公園まちづくり計画の一部変更を提出。これを受けて、再度、検討会・専門部会が開催され、6月に事業者が説明会を開催。6月10日に審査会が開催され、7月5日に「公園まちづくり制度を適用する旨を通知」します。 これで、さきほどから見てきたような事業者提案の「公園まちづくり計画」が、都の計画として採択されたことになったわけです。 そして、その後、関係3区の都市計画審議会に対する意見紹介や、都としての縦覧・意見書提出の期間などを含む、約半年間の審議期間を経て、2022年3月:事業者の提案ほぼそのままの形で、神宮外苑地区・地区計画の変更・都市計画公園明治公園の変更が都市計画決定されたわけです。
- さて結論です。
- この神宮外苑の公園まちづくり計画、あるいは再開発計画とは、ひと言で言えば、 現在の都市計画公園のうち西側のスタジアム通り沿いの土地を、公園まちづくり制度を使って、公園区域からはずし、「容積率適正配分型地区計画」を使って、その土地や公園の南に隣接する伊藤忠本社ある土地に、公園内の余剰容積を移転集約して超高層ビル等を建て、その利益を活用して、屋根付きラグビー場を今の第2球場と建国記念文庫の森のところに新築し、ラグビー場の跡地に新しい神宮球場を新築し、新神宮球場に追い出された会員制テニスコートを絵画館前広場に移設する、 というものです。 しかし、TEPIAが市街地再開発事業に参加しないため、スタジアム通り沿いの土地を外した、残りの狭い敷地の中で、4列の銀杏並木を傷めないような位置に、ホテルなどを含む野球場を納めるのは、到底困難でしょう。 この問題一つとっても、地区全体の建築計画の抜本的な変更が必要でしょう。
- では、どうすべきなのか? 競技を継続しながら、ラグビー場も野球場を建て替え、その費用を、容積移転を受けた超高層ビル開発の利益で捻出する、という虫の良い話は、やはり、建築計画の詳細を詰めていくと、神宮外苑の緑やオープンスペースの量と質を大幅に劣化させない限り不可能である、ということが明らかになってきた、というのが現在の状況でしょう。 容積割り増しで、土地の高度利用を進めて、都民・国民の共通資産であり、東京の大きな魅力の一つでもある、百年以上の歴史のある貴重な緑豊かな空間と、築50年を超える歴史的建造物を潰して、ピカピカのオフィス街・歓楽街や遊園地のようなものを作るというのは、先人がつくり育て護ってきた、将来の世代に受け継いでいくべき、東京や日本にとって、かけがえのないものを失う、まことに愚かなことでしょう。 歴史的建造物である、神宮球場とラグビー場は、今の建物をリノベーション(大幅改修)して、バリアフリー化などを進めつつ、保全すれば、緑やオープンスペースをほとんど損なうことなく、施設を近代化することができます。改修ですから、費用もさほどかかりません。
- 公園区域の変更や、地区計画の変更は、既に都市計画決定済ですが、都市計画決定というのは、いつでも、どのようにでも、変更できるものです。 そもそも、地区計画は、建てられる建物の用途・容積率・高さなどの限度を定めただけのものですし、都市計画公園区域内というのは、木造2階建てなど簡易な建築は別にして、許可を受けた公園施設しか建てられない場所ですから、アセスメントの結果などを受けて、都が許可を下ろさなければ、地区計画には適合しているだけでは、建物を建てることはできません。 しかも、市街地再開発事業の都市計画決定は、アセスメントの結果待ちで、手続きはこれからになりますから、一連の都市計画決定・変更手続きは、最終段階のちょっと前のところに来てはいるけれど、まだ終わったわけではありません。 ですから。このプロジェクトは、まだまだ、抜本的な見直しや、全面的な取り下げの可能性があるものです。 繰り返しになりますが、神宮外苑地区の再整備については、神宮球場とラグビー場の、現地改修保全(リノベーション)を基本に据えたものに抜本的に変更すべきだというのが、本日の私の話の結論であり、提言です。
